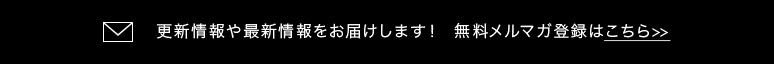PICK UP
2025.03.26
【2025秋冬東京 ハイライト3】クラシックの再解釈や美しさ、ブランドの独自性の追求がポイントに

写真左から「ハイク」「フェティコ」「サポート サーフェス」「タエ アシダ」
パリ・ファッション・ウィークの日程が1週間ずれた影響で、東京のファッションウィークとパリウィメンズファッションウィークの日程が重なり、東京のファッションウィークである楽天ファションウィーク東京は例年より1週間遅い開催となった今シーズン。会期変更にともない、主会場がスパイラルホールとTODA HALL & CONFERENCE TOKYOとなる中で、さまざまな会場でコレクションが行われた。より近くで見られるように、会場の規模を縮小するブランドも増えている。
コレクションでは、クラシックの再解釈や美しさ、ブランドの独自性の追求などがポイントとなった。気候変動に対応したデザインも提案された。
ハイク(HYKE)


Courtesy of HYKE/Photo by Jun Okada(bNm)
吉原秀明と大出由紀子が手がける「ハイク」は、東京・有明アリーナでコレクションを発表した。観客を迎えてのフィジカルでのショー開催は2020春夏以来、約5年ぶり。ここ数シーズンは映像でのプレゼンテーション形式で発表してきたが、今回は観客を迎えたランウェイ形式の発表に踏み切った。
ショーを開催した理由には、映像を依頼していた監督のスケジュールの都合があった。今回は、かつてタッグを組んだ演出家との再共演が実現し、フィジカルショー開催を決めた。「明るいニュースが少ない中で、東京から力強い発信をしたい。東京を拠点に活動している自分たちだからこそできる表現を、ランウェイで伝えたい」という思いも、開催を後押しした。
有明アリーナの広大な空間を活かし、映像制作チームも現場に参加。映像で培った視点を演出にも取り入れ、服の「揺らぎ」や「シルエット」が際立つ構成となった。ショーの臨場感と空間演出の力強さが際立ち、会場全体を包み込むような没入感があった。
コレクションは、ブランド初となるオンブレー調のチェック柄のコートなどからスタート。アメリカンニューシネマに着想を得たニット帽のスタイリングなども取り入れた。ミリタリーテイストやスポーツテーストをベースに、透ける素材を使うことで、軽やかさをもたらした。異素材のドッキング、フリンジ、ファーやボアとの組み合わせ、シャツを履いているようなスカートなど、既存の構造を再構築するアプローチも随所に見られた。ブランドのミニマルな個性にアバンギャルドな要素を加えていた。
コレクションは、秋冬の固定観念に揺さぶりをかけるような提案が印象的だった。シアー素材のトップスや、薄手のロングコートをレイヤードするなど、軽やかで空気をはらんだ装いが多く登場。2枚仕立てのシャツやパンツといった構築的なアイテムも加わり、新たな着こなしの可能性を示した。
5ブランドとのコラボレーションも見どころのひとつ。トレイルランニングをコンセプトにした「ザ・ノース・フェイス(THE NORTH FACE)」をはじめ、「アイヴァン(EYEVAN)」の「イーファイブ アイヴァン(E5 eyevan)」とのアイウェア、「ポーター(PORTER)」の新色バッグ、「エンドカスタムジュエラーズ(END CUSTOM JEWELLERS)」のアクセサリー、「ビューティフルシューズ(BEAUTIFUL SHOES)」のチロリアンシューズなど、多彩なコラボレーションで世界観を広げた。
数年間にわたり無観客での映像発表を続けてきた「ハイク」だが、今回のフィジカルショーでは服の揺らぎや、実在する空間や服の迫力といった、生ならではの魅力が伝わってきた。リアルな場でしか味わえない緊張感と空気感が漂い、コレクションという形式の意義をあらためて感じさせた。
ショー後、吉原は「準備は大変でした。久しぶりのショーだったため、手順を一部忘れているところもありましたが、あらためてショーの醍醐味を感じることができ、エキサイティングでした。興奮するような瞬間もあり、非常に充実した時間を過ごせたと思っています。今後の発表形式についてはまだ決まっていません。ショーにはショーの良さがありますが、映像には映像ならではの面白さがあり、いまはそちらにも魅力を感じています。何かきっかけがあれば、またショーを開催する可能性もあると思いますが、現時点では未定です」と語った。
フェティコ(FETICO)


「フェティコ」は、東京・台東区の「Dance hall New Century」でコレクションを開催した。テーマは“Queen of Curves”。会場のキャパシティの関係により2回に分けて開催された今回。1950年代のピンナップモデル、ベティ・ペイジをミューズに、クラシックなオートクチュールと「フェティコ」らしいボディコンシャスなスタイルを融合させた。
ショーは親密な空間での体験を重視し、観客との距離が近い「Dance hall New Century」で行われた。四角い空間を使ったランウェイでは、モデルが螺旋階段を降りて登場する演出で、フェティッシュでありながら洗練されたムードを創り出した。
コレクションは、ウエストを強調するフィット・アンド・フレアのシルエットを軸に構成。肌の露出を抑えながら、女性の身体の美しさを際立たせる構築的なデザインが並んだ。黒のジャケットとスカートのセットアップやクロップド丈のニットなど、クラシックでありながら現代的な要素が共存する。
特徴的だったのは、ベルトを用いたボンデージ風のアクセサリーと、フリルの柔らかさの対比。レザーやエナメル素材といった質感の異なるファブリックの組み合わせも、緊張感と調和を生み出した。桐生で特別に織られたジャガード素材など、日本各地の産地と連携した生地も使っている。
着想源となったのは、バニー・イェーガーによる写真集『Queen of Curves』で知られるベティ・ペイジ。その曲線的なボディラインと挑戦的な姿勢は、クラシックなトレンチコートやシャーリングドレス、ボディウェアに落とし込まれていた。
また、デザイナーが学生時代、ロンドンの蚤の市で購入したレオパード柄のコートの記憶をもとにしたという、オリジナルのレオパード柄プリントも登場。バラ、チェリー、スズランなどのレトロなモチーフも採用され、50年代的なノスタルジーと現在の感性をミックスさせた。
シルエットは、「ディオール(DIOR)」や「バルマン(BALMAIN)」らによる50年代のオートクチュールを彷彿とさせる構築的な袖やクラシカルなドレスが登場。グレーを基調に、千鳥格子など落ち着いた色調のなかに、くすんだピンクやカーキを差し色として加え、知的な印象を添えていた。
ボディラインの美しさと現代の感性を掛け合わせ、過去の美意識をアップデートした今シーズンの「フェティコ」。クラシックな要素を軸にしながら、女性の自由な選択と表現を尊重する姿勢が貫かれていた。
舟山瑛美は「コレクションタイトルは、ボンデージモデルとして知られるペティ・ペイジの写真集から取ったものです。彼女の自己表現の姿勢に昔から魅了され、憧れてきました。今回は、1950年代のファッションや彼女の曲線美を手がかりに、フェティコなりのクラシックの再解釈を試みました。ペイジの写真はヌードに近いものが多いですが、あえて服を着せることで、その魅力を際立たせる表現に挑戦しました。肌を見せずともフェティコの魅力は成立するのか。その可能性も探りました」と話した。
タエ アシダ(TAE ASHIDA)


昨年、文化庁長官特別表彰を受賞した芦田多恵。今シーズンは“Eternal Threads – Weaving the Past and Future(永遠の糸 ― 過去と未来を紡ぐ)”をテーマに、水上の波紋、空気の乾き、光の動き、自然の中にある色の沈澱など、時間の移ろいを捉え、見慣れた景色が再構築されていくイメージを表現。自然の変化や時間の流れをモチーフに、クラシックと未来、マニッシュとフェミニンといった相反する要素を軽やかに織り交ぜた。
会場は三井ホール。広さではなく凝縮感を重視し、衣服そのものに集中できる空間が選ばれた。ランウェイ演出では、光とモデルの動きによるハレーション効果を狙い、時間が止まったような視覚体験を生み出した。光の動きだけで空気感をつくり出す演出が、コレクション全体のムードを支えた。
コレクションは、自然や土を感じさせる配色と素材によるレイヤードスタイルでスタート。ゴブラン織や透ける素材、レースを組み合わせたクラシックな要素が、現代的な解釈で再構成された。ライダースジャケットと光沢ドレスの組み合わせ、大地を思わせるグラデーション、グリーンのインナーに茶と青が混じるパンツ、茶から赤へと変化するジャケットなどが登場。視覚的にも時間の移ろいが表現された。
中盤でも、ミリタリー調のジャケットやドレープの効いたイエロードレス、青と黄を組み合わせたシャツに黒のアシンメトリースカートなど、都会性と自然性、マニッシュとフェミニンを織り交ぜたスタイルが続く。メンズの構造をベースにしながらも、レディースに落とし込まれたアイテムも目を引いた。
また、気候変動を意識した機能性素材も今季のポイントだ。軽量で保温性に優れたシンサレート入りの薄手フライトジャケットや、ストレッチ性を持つ薄手の新素材フラノなどが採用され、冬場の寒暖差にも対応している。
ショー後半では、ギャザーを多用したボディコンシャスドレスや、アシンメトリーな燕尾服風ジャケット、グラフィカルで光沢のあるドレスが登場。ヌードカラーに墨絵のような色を重ねたチュールプリントドレスや、光をまとうようなドレスは、ファッションとアートの境界を超えたよう。また、カクテル的な要素を持ちながらも、日常に取り入れられるようデザインされたアイテムも多く、伝統と革新、非日常と日常を自然につなぐ構成となっている。
芦田多恵は「ファッションは過去のスタイルが繰り返される中で、新たな解釈が加わり、現代の表現へと変化していきます。今回は、クラシックな要素を今の視点で再構築することを意識しました。また、メンズウェアには多くのルールや定型があり、そうした基盤の上に今のデザインが成り立っていると思いますが、今回はレディースにも、メンズのような考えを取り入れています」とコメント。
また、文化庁長官特別表彰を受賞したことについては「受賞はまったく予想していませんでしたが、30年以上続けてきたものづくりが評価されたことは嬉しかったですし、それ以上に支えてくれたスタッフに喜んでもらえたのがすごく嬉しかったです」と話した。
サポート サーフェス(support surface)


楽天ファッション・ウィーク東京の開幕に先駆け、東京・寺田倉庫E HALLでコレクションを発表した。記念すべき50回目のショーとなった今シーズン、研壁宣男は“クリスタライズ(Crystalize)”をテーマに、美しさと正面から向き合った。
会場に選ばれたのは、コロナ禍中に撮影で使用したことのある寺田倉庫E HALL。ホール型ではなく、ロフトのような開放感のある空間で、クチュール的な美しいデザインを発表することで、逆に美しさを際立たせた。
今回のコレクションでは、グレーのトップスやパンツ、チェック柄ジャケットなど、メンズライクな要素が多く見られた。一方で、ドレープや透け感、フリル、スパンコールといった装飾性を組み合わせることでオートクチュールのように美しいデザインや、柔らかくフェミニンな印象に昇華させた。対照的な素材やシルエットを掛け合わせることで、現代的なミックス感を表現した。
丸みを帯びたコクーンシルエットのドレスやバブルスカート、スキンカラーの透け素材を重ねたスタイリングなどが登場。オートクチュール的な構築性と、日常に取り入れられる軽やかさが共存していた。
また、今シーズンは価格を度外視し、全体の3〜4割を高品質な海外素材とするなど、素材面からも美しさを追求した。
テーマの“Crystalize”には、「美しいものには無駄がないが、無駄がないものが美しいとは限らない」という視点が込められている。「試行錯誤を繰り返し、付け加えたり削ぎ落としたりしながら、最終的に本質だけが残る。その過程こそが結晶化です。洗える、軽い、耐久性があるといった機能性も大事ですが、最も強い機能は『美しい』ということなのではないかと思っています」という研壁。
今回のコレクションは、ブランドにとっての50回目という節目でもあった。横浜の文学館で出会った小津安二郎の言葉「芸術は自分に従う」に強く心を動かされ、「自分の信じる道を迷わず進む」という思いで、まっすぐな視点で美と向き合ったという。
ショーの後、「普段はひねくれた見方をしてしまうのですが、
海外に発表の場を移したデザイナーを除くと、研壁と同じ時期にコレクションを発表していたデザイナーで、今も東京でショーを行っているブランドはいない。「他人と比べない。自分のペースで続けてきただけ。ものづくりが生活のリズムになっているので、やめる理由が見つからない」と話し、今後もショーでのコレクション発表に意欲を見せた。
ピリングス(pillings)


Courtesy of Japan Fashion Week Organization
「ピリングス」は、品川インターシティホールでコレクションを発表した。ブランドとして通算11回目を迎える今シーズンは、前回のクリーンで端正なスタイルから一転し、歪みや荒々しさ、ダメージを前面に出したアバンギャルドな世界観を表現。「未完成の城」を探すという創作の姿勢を通じて、「美しさとは何か」を問いかけたようなコレクションを見せた。
インビテーションとショーのラストルックに描かれたのは、いびつな白いグラフィック。これは、フランツ・カフカの未完の小説「城」に着想を得ており、「完成しないものを目指す姿勢」を示している。理想に到達できないことを前提にしながら、それでも前進するという矛盾と葛藤を、衣服や演出を通して描き出している。
全ルックには、すべて手で編まれたニットが用いられている。ニットに非常に強い洗いをかける縮絨処理(強縮)を施した。素材を高温で洗い、繊維を強く絡ませることで、ニットは大きく縮み、しわや凹凸、よじれが生まれる。
「縮率」が異なる複数の素材を組み合わせている点もポイントだ。たとえば、ある糸は大きく縮む一方で、別の糸はほとんど縮まない。これらを一体化させて編み、縮絨をかけると、一方が引っ張られたりねじれたりすることで、自然な歪みや立体感が現れる、という。こうして偶然性を含んだ独特のフォルムが生まれており、意図的にデザインするのでは得られない、有機的で非対称な造形が強い印象を残した。
また、衣服の内側にあるはずのポケットの袋布や構造パーツをあえて外に露出させ、それらにも縮絨をかけている。これにより、ポケット布がグシャグシャと飛び出し、まるで紙くずのように衣服表面に現れる。こうした手法は、「内と外」や「完成と未完成」の境界を曖昧にし、服という構造物の根本を見直す視点を提示している。
穴の開いたニット、左右非対称なドッキング、スリッパや靴下が付属した衣服など、1980〜90年代のアバンギャルドを想起させるデザインも登場。粗い編み目や造形的なシルエット、動きを拘束したようなデザインも静的な印象も与えていた。
前身ブランド「リョウタムラカミ(RYOTAMURAKAMI)」から10年目、「ピリングス」としては11回目の節目を迎えた今回。村上亮太は「これまでの挑戦を振り返りながら、自分たちにとっての普遍性やクラシックとは何かを改めて考えました。過去に試みてきたさまざまな要素をもう一度見つめ直し、それらを噛み砕いて再構築したシーズンだったと思います。ある意味で、これまでの歩みが混ざり合ったようなコレクションです」と語った。
取材・文:樋口真一