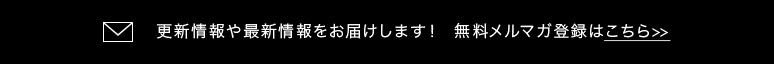PICK UP
2025.02.04
【2025春夏パリオートクチュール ハイライト】クチュールメゾンの威厳と新ディレクターや新進デザイナーによる創造力

写真左から、「ディオール」「シャネル」「ヴァレンティノ」、「ジョルジオ アルマーニ プリヴェ」
メンズに引き続き、2025年1月27日から30日までの4日間、オートクチュール・コレクションが開催された。今季は、公式カレンダー上で28メゾンが参加し、27メゾンだった前季より微増。特に大きな変化は見られなかった。
パリならではのデモやストライキ、あるいは昨夏のオリンピックのような大掛かりなイベントも無く、落ち着きを見せていたパリ。移動に苦労せずに済んだことは大変な負担減となった。
トピックとして一番に挙げられるのが、新任のアレッサンドロ・ミケーレによる「ヴァレンティノ(VALENTINO)」のオートクチュール・コレクション。既にクチュール的な手法でプレタポルテ・コレクションを手掛けてきた彼が、オートクチュールの本場でどのような解釈を見せるのかに注目が集まった
ゲストデザイナーを迎えることで、クチュールラインを存続させているジャン・ポール・ゴルチエによる「ゴルチエ パリ(GAULTIER PARIS)」は、今季はルドヴィック・ドゥ・サン・セルナンが手掛けた。「サカイ(sacai)」の阿部千登勢から始まり、グレン・マーティンスやオリヴィエ・ルスタン、ココ・ロシャなどから数えて8人目。このゲストデザイナーを迎えてのコレクションは、今回で最後になるかもしれないという噂が巡っている。
その他のメゾンに目を向けると、 「シャネル(CHANEL)」はマチュー・ブラジが、「ジバンシィ(GIVENCHY)」はサラ・バートンがそれぞれアーティスティック・ディレクターに就任したことが発表されたが、彼らのコレクションデビューは3月のレディースであり、今季はお預けとなった。オートクチュール・コレクションについては、次回6月に期待したい。
ディオール(DIOR)


服の礎となるテーラリングを再考察し、先代達のクリエーションに思いを馳せながら、クラシカルモダンなクチュールウェアを提案したマリア・グラツィア・キウリによる「ディオール」。ロダン美術館内の特設テントにてショーを発表した。内部を飾ったアートワークは、リティカ・マーチャントによって考案され、インドの刺繍工房や工芸学校の生徒たちの手で制作されたもの。ショー後に5日間だけ一般公開された。
1958年にイヴ・サン・ローランがディオールのために考案した、肩から裾に向かって広がる「トラペーズライン」や、1952秋冬オートクチュールコレクションでムッシュ・ディオールがデザインした「ラ・シガール(仏語で蝉の意)」のシルエット・素材使いを引用。シルクで覆われた木製ビーズを飾ったコートや、スタンドカラーのテールコートにその影響が見て取れた。
しかし、そんな中で鮮烈だったのが、西洋服飾史を紐解いたかのようなバスルやクリノリンの数々。イングリッシュレースをあしらったボディースやランジェリードレスは、おとぎ話の主人公のようなファンタジックな装いを見せる。クリノリンのドレスには、花が咲き、実がなり、昆虫がとまる。中世のコスチュームを思わせるプリーツレースをあしらったり、オーガンザの大きなバラや、羽を模したオーガンザのパーツが飾られたり。そのバリエーションの多さと、それぞれのルックに駆使される刺繍やカッティングの技巧の高さに圧倒される。「ディオール」のクチュールメゾンとしての威厳をあらためて示したかのようなコレクションとなった。
シャネル(CHANEL)


スタジオのデザインチームによる2回目のクチュールコレクションは、グラン・パレを会場に発表された。CCマークの形に橋げたを作り、その上に客席を設置。壮大なスケールのランウェイを、オプティミスティックな空気感を漂わせるクチュールウェアをまとったモデル達がウォーキング。
エッジーさとは距離を置き、クラシカルかつフレッシュなアイテムで構成。今季は特にガブリエル・シャネルのクリエーションにオマージュを捧げ、このメゾンの魅力を余すことなく伝える内容となっている。ただ、シャネルの歴史をなぞるのではなく、ツイードのスーツをスカートではなくショートパンツに変えたり、フルレングスのドレスには、スカート部分にシフォン素材をあしらって軽さを出したり。全てモダナイズされている。
前半はパステルカラーをメインに、コーラルレッドやパープル、グリーンやブルーなどを差し色にし、後半はミッドナイトブルーや黒に変化するも、シルバーやゴールドで締めくくり、朝から夜へのサイクルを色で表現。
あしらわれるブレードやボタン、ベルトのバックルといったディテールも美しく、それぞれのルックを引き立て、マッチするように計算し尽くされている。シューズも含めて、全てを自社で作成できる「シャネル」は、クチュールメゾンの中でも稀有な存在。様々な職人達の手を経たものが重なり合うことで、完璧で美しい物が完成する。そんなことをあらためて思い知らされた今季だった。
ロナルド・ファン・デル・ケンプ(RVDK RONALD VAN DER KEMP)


Courtesy of RVDK RONALD VAN DER KEMP
昨年6月のオートクチュールには参加せず、9月に自らのキャリアの出発点となったニューヨークで、ブランド10周年記念のショーを開催したロナルド・ヴァン・デル・ケンプ。再び発表の場をパリに戻し、オランダ大使公邸にて最新コレクションを披露した。
今季もアップサイクルされた素材をあしらい、自由なクリエーションを見せている。タイシルクを用いたラフルのドレス、様々な断片をパッチワークしたドレス、ヴィンテージのドレスを再利用したドレスなど、素材から発想を膨らませたと思われるアイテムが登場。荒々しさも見られるが、それを補って余りある服への情熱を感じさせた。
ゴールドチェーンを飾ったツイードのアンサンブル、洋の東西を問わずに様々なドレスから採取した素材を幾重にも重ねた着物風ドレス、バラのプリントのブラトップとチェックのタフタのスカート、そのどれもが偶発的な美しさと魅力を兼ね備えている。
部屋を飾る中世に織られたフランドルのタペストリーと、現代の職人的な手仕事が呼応。美しいコントラストを見せていた。
ジョルジオ アルマーニ プリヴェ(GIORGIO ARMANI PRIVÉ)


“Lumières(煌めき)”と題し、文字通り宝石のような輝きを放つコレクションを発表した「ジョルジオアルマーニ」。会場は、フランソワ1世通りにオープンさせたパラッツォ・アルマーニ。イタリアの大理石で彩られた荘厳なインテリアと、光を反射するクリスタルのドレスは美しいコントラストを見せていた。
アルマーニらしいパンツスーツでスタート。パンツのバリエーションが豊かで、サルエルパンツや東洋風の文様をジャカードで表現した素材によるものなどが登場し、随所にエキゾティズムが感じられた。
世界中を旅しているかのような気分にさせられた今季。東南アジアのイカット模様のジャケット、赤をメインカラーにした中国風の刺繍を施したアンサンブル、南国の風景を水彩画のように表現したドレス、日本の桜を思わせる花を刺繍したチュールを重ねたベアショルダーのドレス、アラベスク文様のジャケット。様々な国の文化から影響を受けたアイテムが、アルマーニのコードできらびやかに形作られている。
宝石のようなマルチカラーの大きなクリスタルを刺繍した、全面にスパンコールを刺繍したコートドレスやホルターネックのドレスは、地の色を黒やグレーにしてエレガントに仕上げている。後半にはクリスタルの輝きが眩いドレスが連続して登場し、その美しさに圧倒された。クチュールライン20周年の記念すべきコレクションは、実に93ものルックで構成。フィナーレでは、今年91歳を迎えるジョルジオ・アルマーニに盛大な拍手が送られた。
ユイマナカザト(YUIMA NAKAZATO)


オスマン大通り沿いのレンタルスペースに砂丘を作り、儀式を思わせる荘厳なショーを開催した「ユイマナカザト」。風化を意味する“Fade”と題したコレクションは、太古の時代に海の底だったサハラ砂漠にイメージを求め、実際にモデルと共に撮影を兼ねてサハラ砂漠を車で旅した。GPSが繋がらず、遭難しかけたそうで、その時の記憶もコレクションに少なからず影響を与えたという。
チェーンでトリミングしたドレスやトップス、チェーンが重なり合うアクセサリー。今季は金属の光沢感とマットな素材とのコントラストを描く。チェーンを繋いだオールインワンも登場したが、使われた糸は、隕石とサハラ砂漠の化石を粉砕して染めた土に還る糸を使用している。
最終ルックは、それまでのショーの流れをより一層濃密なものにする。中里唯馬本人が登場し、砂丘に埋まったセラミックを繋いだドレスを掘り起こし、チェーンドレスをまとった男性モデルに着せた。1000時間を要したというドレスは、身にまとい立っているだけで身体に大きな負担を与える。
中里は、「オートクチュールは美しいものを追求するファッションという側面がありつつ、マスプロダクトではないものを創り上げる部分もある」とし、実用性を排除した極端に重い服が完成。えもいわれぬ空気感に見る者は圧倒され、会場からは割れんばかりの拍手が起きたのだった。
ヴァレンティノ(VALENTINO)


“Vertigineux(めまい)”と題したコレクションを発表した、アレッサンドロ・ミケーレによる「ヴァレンティノ」。ヴァレンティノ・ガラヴァーニが残したアーカイブを紐解き、オリジナルのアイデアを解体し、増幅し、集積し、様々な要素が加えられる。白のコレクションからインスパイアされたマクラメレースのドレスは、モチーフが集中してまるで鎧のような重厚感が生まれ、フローラルプリントのドレスはクリノリンを合わせてロココ的な解釈がされている。時代性や国籍などあらゆる境を超えた、新しいジャンルのクリエーションが生まれていた。
アルルカンモチーフのグランバルでスタート。トップ部分はシフォン、スカート部分はチュールで構成。アンバランスな中にバランスが感じられ、不思議な違和感に囚われる。プリーツシフォンに鎧のようなパネルドレスを合わせたルックや、トレーンを引くシフォンのフリルスカートにマトラセのジャケットを合わせたアンサンブル、プリーツスカートに東洋風のモチーフを甲冑のように並べたロングドレスなど、本来ならば調和しないもの同士を敢えてぶつけている。
キルトのようなパッチワークの巨大なドレスには、16~17世紀にヨーロッパの王侯貴族の間で流行したひだ襟を飾り、オーガンザのラフルで覆われたゴージャスなドレスには、敢えて民俗的な刺し子のジャケットをコーディネイト。家具の背もたれや座板のクッション部分に用いられる刺繍の巨大なドレスや、凹凸あるラフィアをミックスしたニットによるアンサンブルなど、常人の想像を遥かに超える強烈なルックが並んだ。
ヴィクター&ロルフ(Viktor&Rolf)


これまで通り、コンセプチュアルな作品作りに徹した「ヴィクター&ロルフ」。イヴ・サン・ローランがオートクチュールのショーを開催していたことで知られる、ナポレオン三世様式の重厚な内装のウェスティン・ホテルの広間を会場に、トレンチルックで統一するというシンプルで明確なコレクションを披露した。
モデルが登場する度に「○○番目のルック、ベージュのガザール製トレンチ、白のガザール製シャツ、ブルーのガザール製パンツ」とAIがアナウンス。全て同じアイテム・色・素材であるため、数字のみが増えて行く。ガザールは、硬い絹糸を強く撚った二重糸で作られた平織りの織物で、独特の張りがあり、その形状保持力から立体的な造形に適している。今季は、イタリアのルッフォ・コリ社によるシルクガザールを実に900m分使用し、素材の特性を生かした服作りを見せた。
トレンチは、袖にパネルをあしらったり、全体にしわを寄せたり、リボン結びを飾ったり。ビスクドールにトレンチドレスを着せたルックも登場した。シャツもバリエーションを見せ、襟が大きくなったり、シャツドレスになったり、ジゴ袖を取り付けられたり。それらに合わせて、パンツの丈は伸び縮みし、ボリュームも異なっていく。しかし、トレンチ、シャツ、パンツという3アイテムの組み合わせに変化はない。
トレンチとシャツとパンツという、本来ならばワークウェア・ユニフォームにカテゴライズされるアイテムを、敢えて最高品質のシルク素材で仕立て、オートクチュールのレベルに到達させる。ヴィクター&ロルフは、またも前人未到の領域を開拓したのだった。
ゴルチエ パリ(GAULTIER PARIS)


ゲストデザイナーにルドヴィック・ドゥ・サン・セルナンを迎えた「ゴルチエ パリ」は、本社パーティルームを会場にショーを開催した。コレクションタイトルは“Le Naufrage(難破船)”。
1998年の春夏コレクションで登場した赤いビーズをあしらった船型のヘッドドレスを羽で表現したり、綿入りのパーツを装飾にした2008年の秋冬コレクションを彷彿とさせるNaufrageの文字をあしらった赤のドレスを制作したり。これまでのゴルチエのクチュールコレクションをなぞりながらも、ドゥ・サン・セルナンの露出度の高い挑発的な作風を全面に出して、官能的なシースルードレスやコルセットドレスを発表。
無数のアイレットで構成されたコルセットと、スパンコールを刺繍したスカートのマーメイド風アンサンブルでスタート。コルセットの構造はジャケットにあしらわれ、シルクジャージーのプリーツのトップスに変化し、レザーのロングドレスやスワロフスキーによるタータンチェックのクリスタルメッシュドレスに応用される。
砂をイメージしたビーズ刺繍のワンショルダードレスとビーズを刺繍したロープのアンサンブル、深海の生物を思わせるクロコダイルレザーのドレス、イカリの形をしたヌーディなレースドレスなど、海を想起させるルックが印象的。ゴルチエのアトリエの高い技術により、ダークで退廃的なアイテムが完璧に仕上げられていた。
ミス ソーヒー(Miss Sohee)


かつてカール・ラガーフェルドも居住した、18世紀建立の館ポッゾ・ディ・ボルゴを会場にショーを開催した「ミス・ソーヒー」。今季は、自らのルーツである韓国の文化的背景を西洋のクチュールにミックスし、自らが好むフローラルモチーフで飾り、貝のフォルムをあらゆるルックに反映させている。
シャンティレースによるボディースと、貝のフォルムのレザーコルセットをまとったココ・ロシャでショーはスタート。二枚貝を想起させるヘッドドレスをあしらったボディスや、「ヴィーナスの誕生」を思わせる貝のドレス、クロコダイル風刺繍のオフショルダーのドレス、花が川に流れているかのようなブルーのロングドレス。それぞれ何かしらのストーリー性を帯びている。
李氏朝鮮時代の貴族の装いをイメージしながらも、朝鮮庶民の実用的な民俗絵画である朝鮮民画に触発され、引用されたモチーフをコルセット部分にビーズで刺繍したり、長いトレーンのストールのモチーフにあしらったり。
韓国独自の技法を用いたマザー・オブ・パールの螺鈿漆器をクラッチバッグとして用い、黒髪のヘッドピースなども含めて、韓国のアイデンティティを示すアクセサリーとなっていた。