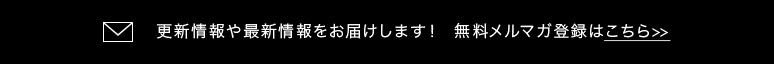PICK UP
2024.06.29
【2025春夏パリメンズ ハイライト3】昨今の日本のメンズブランドの隆盛とその理由

写真左から「ダブレット」「カラー」「ベッドフォード」「ホワイトマウンテニアリング」
パリコレクションを主催する、パリオートクチュール組合によるメンズの公式カレンダー上では、参加する69のブランドのうち、15が日本勢だったことは既に伝えた通りである。実に総数の2割を超えており、これまでで最高占有率となった。公式カレンダー外でショーを発表した「MASU」や「バウルズ」もおり、日本のブランドの多さには目を見張る程である。
一体どうなっているのか。その鍵を握るのが、メンズコレクション会期中に北マレ地区で毎シーズン開催される合同展示会「ショールームトーキョー・イン・パリ」である。
世界を舞台に活躍が期待されるデザイナーを選定・表彰し、海外における展開を支援するTOKYO FASHION AWARDの受賞者が参加し、これまでに60ものブランドをサポート。その中には、パリ・メンズコレクションに毎シーズン参加している「サルバム」、「キディル」、「オーラリー」、「ベッドフォード」、「ターク」、「ダブレット」といった錚々たるブランドが含まれている。
主催する日本ファッション・ウィーク推進機構のコレクション事業ディレクター、今城薫氏によると、支援期間終了後は、各ブランドは自力で展開していく外は無いそうだが、昨今のメンズファッションの需要の広がりと共に自ら業績を伸ばすブランドが増え、パリで定期的なショー開催を可能にする流れが出来上がっているようである。
今回2シーズン目の参加となるニットブランド「コウタグシケン」の具志堅幸太氏によると、渡航費、宿泊費、展示会参加費の全面的なサポートを初回に得られたことは大きく、「ショールームトーキョー」に参加すること自体が経験値を上げることとなり、ブランドの方針やクリエーションについて刺激になっているという。
合同展示会主催者のサポートとブランド側の努力によって、日本のブランド力が高まり、各ブランドは事業展開のチャンスを得ることが出来る。それが、パリ・メンズコレクションで、日本のブランドの参加が増えている理由の一つとなっているのだった。
それにしても、日本ブランドがあまりにも多い。主催のパリオートクチュール組合から、参加国の偏りの調整を理由にはじき出されないことを祈るばかりである。
カラー(kolor)


アンリ4世高校の中庭でショーを行った、阿部潤一による「カラー」。今季はテーラードやブルゾンといったワークウェア・ユニフォームを独自の解釈で再構築し、ディテールに大胆な遊びを加えて新たなアイテムに仕上げている。
表の布を剥ぎ取り、襟の内側のステッチを見せたジャケット、2枚のニットを重ね着したかのようなトロンプルイユのジレ、内側にベルトでポケットを垂らしたシースルーベスト。一見オーソドックスに見えるようなものでも、技巧を凝らした特別感を帯びた仕上がりになっている。
レディースコレクションも目を引く。ジゴ袖のようなシャツを重ねたスリーブレスジャケットや、スリーブを極端に太くし、しわ加工を施したシャツ、トレーンを引くチュールのトップスを重ねたミニドレスなど、絶妙なバランス感を見せるルックが続いた。
「服はこうあるべき」と考える、ある種保守的な視点を持つ人間にとっての違和感を、丁寧な手仕事によって服に加えることで、カジュアルでスポーティな中に独自のエレガンスが生まれるのかもしれない。そんなことを思わせたコレクションだった。
ホワイトマウンテニアリング(White Mountaineering)


Courtesy of White Mountaineering
相澤陽介によるホワイトマウンテニアリングは、パレ・ドゥ・トーキョーを会場にショーを開催。凝った素材やディテールを配しながらも、オーソドックスなシルエットのアイテムでコレクションを構成した。
ピンストライプのシャツやショーツ、チェックのシャツなど、美しい色味のアイテムには、カジュアルでスポーティなニットプルを合わせて、リラックスしたムードを見せる。隠しポケットを配したパーカや、身頃をダブルにしてジップで開閉するボンバースなど、目新しいアイテムを挟み込みながら、着易さを追求したようなフラットなアイテムを提案。
中でも目を引いたのが、墨染めのように見える、実はジャカード織によるファブリックをあしらったアイテム。カジュアルでシンプルな作品が多い中、強い印象を残した。
前シーズン同様、コラボレーションアイテムも散りばめられており、アンブロによるブルゾンやポロシャツ、リカバリーサンダルメーカーの「リグ(rig)」によるサンダル、リーボックによるスニーカーなども登場した。
ダブレット(doublet)


日本の「推しワールド」に焦点を当てた、井野将之によるダブレットは、テュルビゴ通りのテュルゴー高校の中庭でショーを開催した。自らの「推し」を見つけ、全身全霊応援する日本の「推し」の文化を、昭和の応援団や現在のオタク文化と結び付けて、一つのコレクションとして表現。会場では「指差して!」や「キスして!」などの文字が入った手作りのオタク団扇が配られた他、協賛のオタフクソースによるたこ焼きが振舞われ、まるで縁日のような様相だった。
学生たちが登場し、人工合成による構造タンパク質素材のスパイバーなどの協力企業をプリントした横断幕を広げ、ランウェイが仕切られた。今季は、特にダブレットを応援して来た企業への応援返し、という意味合いも込めていた。
日本の高校・大学で見られる応援団ルックでスタート。クラッチはポンポンを思わせるグリッターラメ製。ラメニットが装飾として付いたジャケットも登場。チアリーダーのイラストが刺繍されたポンポンつきニットプルや、ペンライトを入れるためのオタ活用ベスト、缶バッジやキーホルダーを飾る「痛バッグ」などが登場。
架空のキャラクターをプリントしたTシャツとデニムパンツや、「推しが尊い」のネオンイラストをプリントしたチビTなど、ユーモラスなアイテムには、美しいシルエットのテーラードやライダースジャケットがミックスされる。毎シーズンながら、遊び心のあるアイテムとシリアスなアイテムのバランスも絶妙である。
最後に「推ししか勝たん」と書かれた団扇を持って井野将之が登場し、拍手喝采となった。
ターク(TAAKK)


パレ・ドゥ・トーキョーでショーを開催した、森川拓野による「ターク」。グラデーションやアプリケーションなど、このブランドが得意とするファブリックやテクニックが今季も登場したが、それぞれを進化させて完成度を極め、一つの頂点を見せたコレクションとなった。
140mものリボン状に割いたファブリックを縫い付けて、唐草モチーフを描いたセットアップや、グラデーションのロングコートなどは、それぞれ色とシルエットの美しさにも目を奪われる。特に、袖から身頃に掛けてグラデーションになっているジャケットは目新しく、優美な雰囲気を漂わせていた。
リボン状に引き裂いたファブリックを縫い付けたかのようなプリントモチーフのセットアップは、トロンプルイユ(だまし絵)的なルック。スプレー染めを施したパンツは独特の立体感を見せ、ギャザーを寄せたシャツや粗く編まれたニットを引き立てる。
ジャカードの織り部分を切りっ放しにした素材によるセットアップや、ひだ状にリボンを縫い付けたジャケットなども独特の質感を見せて美しい。特に目を引いたのが、薬品でモチーフだけを残し、その上から厚みのある塗料をプリントした、レースのような素材によるアイテム。以前から用いていた技術を進化させたという。このブランドにまた一つアイコンが増えたようだ。
キディル(KIDILL)


末安弘明による「キディル」は、ルイ16世やマリーアントワネットなど、フランス革命期に処刑された人々を埋葬していたマドレーヌ墓地跡に、ルイ18世が資金調達して建てた贖罪礼拝堂の回廊を使ってショーを行った。
今季は、theOGMとYeti Bonnesからなる音楽デュオ「ホラー(Ho99o9)」との出会いと交流にインスピレーションを得て、「Ho99o9」の文字やアートワークをあしらった様々なアイテムが登場。そして、原宿のストリートスタイル、特に「ロリータ」から着想を得たルックもブレンドしている。また「アンブロ(UMBRO)とのコラボレーションによるスポーツジャケットやゲーマーTシャツも登場。
ヴィンテージのメタルTシャツをマスクに使用し、「Ho99o9」のアートワークを配したノースリーブジャケットでスタート。錠前で開閉するアニマルモチーフのオールインワンには、
袖にウエストポーチが付いたチェックのブルゾンや、ダメージニットを組み合わせたジップアップセーターなど、造形的な面白さを見せるアイテムも。「Ho99o9」の文字をニットで表現したダメージニットには、架空のキャラクターをプリントしたセットアップをコーディネート。チュールのスカートを配したロリータ風のドレスも登場。
最終ルックは、様々なヴィンテージファブリックを用いて仕立てた、ぬいぐるみのような立体的なジャケットを羽織ったブラックドレス。パンキッシュな毒々しさとロリータの可愛さ、相反するものが見事にミックスされた、コレクションを象徴するかのようなルックだった。
オーラリー(AURALEE)


Coutesy of AURALEE
岩井良太によるオーラリーは、カール・ラガーフェルドが居住したことでも知られる18世紀建立のポッゾ・ディ・ボルゴ館にてショーを開催した。緑豊かな公園を横切る多様な人々の様子を、一つのコレクションの中で表現した今季。「オーラリー」らしい美しい素材をあしらった、バリエーション豊かなアイテムで構成している。
パジャマにコートを羽織ったようなルックでスタート。ギンガムチェックは、今季のキーモチーフとしてシャツなどで登場し、各ルックを明るく照らす存在となっていた。フランスの新聞「ル・モンド(Le Monde)」を手にしたサラリーマン風、メモを持ったご婦人風、ランニングをしに来た女性風など、ストーリーをイメージさせるルックが続く。
バックスキンのショーツには、スポーティなブルゾンと薄手のカシミア素材のニットをコーディネート。今季は特に、カシミア100%の平織り素材を開発して用いている。
コートやブルゾンで使用されているキャンバス地は、高品質の超極細ウールで作製し、チノクロスやギャバジンは手触りを重視した加工を施したといい、繊細な素材使いがコレクション全体をより一層エレガントに見せていた。
ベッドフォード(BED J.W. FORD)


山岸慎平による「ベッドフォード」は、アンリ4世高校の中庭を会場にショーを開催した。労働の中で感じる休息への渇望をイメージし、オフィスワーカーから現場作業員まで、様々な職業人が家へ帰る時の姿をコレクションとして描いて見せた。
くたびれたような風合いを出した、オーバーサイズのレザーブルゾンでスタート。カーディガンには小さな鐘が縫い付けられ、就業の音を奏でる小さな鐘を象徴。休息を望む心を象徴した羽のブローチが飾られたトレンチコートには、鐘が縫い付けられたストラップで袖元を固定。
ワークウェア風のフード付きオールインワンには、ジャケットとシャツとネクタイが合わせられ、ホワイトカラーとブルーカラーを折衷。Working Class Theaterの刺繍の入ったキャップと工具入れのようなボックスバッグも目を引いた。
擦れて色が落ちたかのような加工を施したワークジャケット、労働者の涙を思わせるドロップモチーフのデボレ素材のシースルーシャツ、長く伸びたシャツなど、ありきたりのユニフォームを大胆に変換。このブランドのアイコンとも言える、ゴールドチェーン&ボタンをあしらったシャネルジャケット風のアイテムは、今季はニットカーディガンとして登場し、その対極ともいえるローエッジのデニムショーツに合わせられた。
エム エー エス ユー(MASU)


Courtesy of MASU
今年、FASHION PRIZE OF TOKYO 2024のグランプリを受賞した後藤愼平による「エム エー エス ユー」は、トラッドとアイビーに焦点を当て、捻りを加えたアイテムでコレクションを構成した。
絞りのボーダーシャツでスタート。合わせられたのは、床まで届くバギーパンツ。アーガイルのニットプルは所々シースルーで編まれ、下に合わせたネクタイが透けて見えている。ブレザーのカフスには無数の金ボタンが並び、所々つまんだパンツには不思議な膨らみが見られた。ポロシャツとクロップドパンツにはサテンリボンの付いたバレリーナシューズが合わせられ、スプレーペイントのニットベストにはタータンチェックのスカートがコーディネートされ、独自のマスキュリンフェミニンを実現。
長く伸びたネクタイ、裾を引き摺る程長いパンツ。対照的に身体にフィットさせたブルゾンやジャケットをコーディネートし、トラディショナルな装いをモダナイズしている。
日本のアイビールックの生みの親とされる石津謙介のポートレートをプリントしたトレーナーや、ツタをプリントしたレザーブルゾンが登場。ツタ(アイビー)のからまる校舎を有する歴史ある大学、を意味するアイビーリーグから発生したアイビーファッションに因んだ。
バウルズ(vowels)


アメリカを拠点とするブランド“モンマルトルニューヨーク”のデザイナー、八木祐樹が今年立ち上げた“バウルズ”のファーストコレクション。パリ工芸博物館の広間を会場に、華やかさを加えたストレートなカジュアルウェアを発表した。
文化服装学院、アントワープ王立芸術学院、そしてパーソンズでファッションを学んだ八木は、様々なブランドでデザイナーとして関わり、2016年にヘイリー・シャンポーと共に“モンマルトルニューヨーク”を設立。1年の準備期間を経て、今年の5月に「バウルズ」をスタートさせた。日本産の素材にこだわり、製造も全て日本で行い、茶道や武道で用いられる“守破離”の手法を念頭にクリエーションを行っている。
「単純に綺麗だから」との理由で登場したフローラルモチーフは、ワークウェアパンツやウエスタンシャツを彩り、曲線が揺らぐニットポロにもポイントで花が刺繍されている。
ブランドロゴが無数に踊るコートやパンツが登場したが、これは富ヶ谷にあるヴィンテージショップ「ミスタークリーン(Mr. Clean)」とのコラボレーションによるファブリックを用いたもの。ヴィンテージ素材を解体し、カットしたパーツをアップリケするという、気の遠くなるような作業を経ている。シンプルなシルエットの中に、繊細なディテールを散りばめ、ブランドの精神を象徴するような作品となっていた。
取材・文:清水友顕(Text by Tomoaki Shimizu)
画像:各ブランド提供