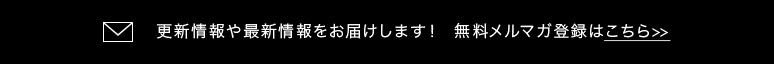PICK UP
2024.03.10
【2024秋冬パリ ハイライト3】 パリコレの要となる日本人デザイナーたち

写真左から「ヨウジヤマモト」「イッセイ ミヤケ」「アンリアレイジ」「アンダーカバー」
パリを拠点とする「ジュンコ シマダ(JUNKO SHIMADA)」を除き、10のブランドが日本からパリコレクションに正式参加している今季。全108ブランドの中での10ブランドで、1割弱となる。約2割を日本のブランドが占めているメンズコレクションとは大きく異なるが、それでも比率としては大きく、日本の数を超える外国勢は他に見当たらない。昨今の極端なユーロ高によって、各ブランドの負担も大きなものになっているはずで、敢えてパリ進出をして採算が取れるのか。パリコレクションに参加することで付く箔と、経費の重みとの両天秤となっているに違いない。
一方の、パリコレクションを見る側についても同様で、状況は過酷である。日本の媒体の取材者数は増えているが、高額な宿泊料を避けてホテルのグレードを落とす傾向は続いており、更に移動のためにチャーターしていた車を取り止める、あるいは複数の媒体で乗り合いにして経費削減をするケースも見られた。日本からのバイヤーも、出張者数を減らす、あるいは出張そのものを取り止めるところも。そもそも日本からの出展者数が減っている合同展示会だったが、バイヤーも減り、益々閑散としていたという声が多く聞かれた。ユーロ高が長引く限り、この傾向は続きそうで、少なくともパリ・オリンピックまでは我慢を強いられそうである。来シーズンの9月に、どのように転じるかを期待したい。
パリコレクション最終リポートは、日本のブランドを特集して紹介する。
シーエフシーエル(CFCL)


パリコレクションに参加して2年が経ち、遂に正式なショーの発表となった高橋悠介による「シーエフシーエル」。ショー前に弦楽四重奏楽団が登場し、耳をつんざくような音を奏でながら楽団員はリズミカルに絶叫。コレクションタイトルは韻律を意味する“Cadence”で、テーマと音楽はマッチしていたが、恐怖感さえ抱かせた。
高橋は「過度な装飾を削ぎ落した実用的な衣服は、日常を豊かにしてリズムを生み出す」とし、リラックスと緊張を繰り返す中で、オケージョンを問わない、控えめなエレガンスを漂わせるニット・ウェアを提案している。
ジャケットは、1つボタンでシームポケットに仕立ててディテールを削ぎ、平面のドレスにはリブを配すことで立体的に仕上げている。それらをアセテートと再生ポリエステルで制作。B Corp認証を得ているブランドらしく、今季も全体の素材の8割以上に認証素材を使用している。
角度によって表情が変わる細かな凹凸で編まれたストライプのシリーズや、レーヨンのモール糸を混ぜて編み、ビロードのような光沢感と手触りを出したシリーズなども目新しい。前シーズンでも登場したが、職人が一つ一つスパンコールを縫い付けた、ドレッシーなシリーズで締めくくった。
マメ クロゴウチ(Mame Kurogouchi)


佐賀県を旅し、その地で触れた陶器、古唐津からインスパイアされた黒河内麻衣子による「マメ クロゴウチ」。コレクションタイトルは“Fragments”で、陶片のイメージをコレクションに反映させている。会場は前シーズン同様、建築家の緒方慎一郎氏によるレストラン「OGATA paris」。
モヘアのニットベストには、土色に染めたボタニカルジャカード素材のパンツを合わせ、土の上を流れる釉薬をイメージさせる。マニッシュなスーツ類は、装飾的な要素を削ぎ落して、一切の無駄を省いた陶器を思わせるシンプリシティを表現。唐津焼のモチーフとなった草花はコード刺繍のモチーフとなり、三島唐津の細かな連続文様はジャカード素材によるドレスやニットに引用される。
むら染めのアルパカウールのコートは、斑唐津のオーロラのような釉薬をイメージ。シルクウールのワンショルダードレスやオーバーサイズのパジャマシャツは、京都の職人の手によるもので、餅米を生地に塗って乾燥させることで生じるひび割れに染料を染み込ませる手法で作り上げたもの。そうして、焼き物の貫入を想起させるアイテムが完成した。
古唐津というテーマを深く掘り下げて、様々な表現や手法を用いて一つのコレクションを創り上げた今季。静寂をも湛える渋い内容ではあるが、その構成力と独自のエレガンスに圧倒された。
アンリアレイジ(ANREALAGE)


森永邦彦による「アンリアレイジ」は、アレクサンドル三世橋の袂のイベントスペースにて、最新コレクションを発表。
藤子プロとのコラボレーションによる、「ドラえもん」のイメージを全面的に押し出した今季。タケコプターをイメージしたドローンをランウェイに登場させる予定だったが、技術的な問題が起きて叶わず。当初からの予定だったランウェイショーではなく、急遽モデルを立たせた状態で見せるプレゼンテーション形式での発表を余儀なくされた。
ただ、コレクションは「アンリアレイジ」らしい手法を見せ、完成度の高さを見せていた。様々な体型・体格を持つ人々ために、ファッション業界は様々なサイズ・形の服を作ることで対応しているが、森永は発想を転換。球体や立方体、多面体に合わせて服を作り、それを人間に着せれば、サイズも形も関係が無い、という理論である。
そうして出来上がったアイテムは、それぞれが独自のフォルムとボリュームを見せ、メンズとレディースの垣根も感じさせない。今季は「リーボック(Reebok)」やダウンジャケットの「ヘルノ(HERNO)」とのコラボレーションアイテムも登場し、これまでに無いスポーティな要素が見られた。
アンダーカバー(UNDERCOVER)


日常着に独自の捻りを加えた高橋盾による「アンダーカバー」。カジュアルウェアからタキシードスーツまで、普遍的なアイテムをアップデートし、圧着のテクニックを用いて全く新しいものに作り替えている。コレクションタイトルは“Watching a Working Woman”。映画監督、ヴィム・ヴェンダースによる同タイトル作品の朗読がBGMだった。
ファーストルックから、「アンダーカバー」らしい異質さを漂わせていた。キャミソールとデニムパンツとニットリブのアンダーが一体型になっている。ニットドレスとピンストライプのマニッシュのパンツも1つのアイテムに融合し、カーディガンとモヘアのワンピースも全てが1つの服になっている。
「アンダーカバー」らしい毒々しさやユーモアを感じさせながらも、ジャケットとコートのミックスやファーとレザーのミックスコートなどはエレガントな仕上がり。
ラメのフリンジ素材と綿入りのスポーティなブルゾンのミックス、あるいはラメフリンジとコートをミックスしたドレスも、不思議なアイテムであるにしろ、美しいバランスを見せている。今季はこれまで以上に大胆さの目立つ、しかしこれまでに見られなかった方向性を示し、唯一無二のオリジナリティを漂わせるコレクションとなった。
イッセイ ミヤケ(ISSEY MIYAKE)


© 2024 ISSEY MIYAKE INC./Photo by Frédérique Dumoulin-Bonnet
“What Has Always Been”と題し、仕立てたものではなく、布をまとうことに向き合ったコレクションを発表した近藤悟史による「イッセイ ミヤケ」。国立移民史博物館にてショーを開催した。BGMは中野公揮による生演奏。
一定の時代背景や環境に囚われず、着る人の自由意思でフォルムの変換が可能な服を考察。太古の昔の服や遊牧民の服を思わせながらも、同時にウルトラモダンにも見え、これまでにない新しさが生まれていた。
和紙とストレッチ糸を折り合わせた一枚の布のシリーズでスタート。単に身体に巻き付けるのではなく、彫刻的なシルエットを描いている。アサガオをイメージしたシリーズは、グラデーションを描き、帽子を被っているように見えるが、服と一体型の無縫製ニットによるもの。
一着で重ね着をしているかのように見えるニットのシリーズも、無縫製で作製され、2色に分かれている部分を上げ下げしたり、身体や腕を通す位置を変えたりすることで、様々な着方を楽しむことができる。ドレッシーな2つのシリーズは、コレクションの中でも一際ドラマティックだった。採取した草花をモチーフにしたポンチョとロングコートのシリーズは、コットンとウールの収縮差によって原画の刷毛目まで表現。円形と直角の型を用いてハンドプリーツを施したシリーズは、彫刻のようなシルエットを描き、動く彫刻のよう。厳格さの中にプレイフルな要素を散りばめたコレクションとなっていた。
ヨウジヤマモト(Yohji Yamamoto)


彫刻的であったり、グラフィカルであったり、装飾性に重きを置いたコレクションを発表した「ヨウジヤマモト」。
冒頭では、首元や肩などにパーツを配した、アシメトリーのコートやドレスが登場。角張った装飾は布で表現されることで丸みを帯び、円でも直角でもない、不思議な融合を見せる。
黒のイメージが強いこのブランドだが、グレーや白がミックスされ、そのコントラストによって装飾がより一層浮かび上がって見える。
チェックのシリーズでも角張った装飾が各アイテムを彩っていたが、マスキュリンな中にフェミニンな側面が感じられ、そのコントラストが興味深い。コードでパーツを繋いだドレスには、インナーに白や赤のシャツドレスを合わせて色の違いを強調。次から次へと黒のイメージを打ち破るルックが登場し、最後にヒップラインを大きく見せるチュール製のバッスルを合わせたコートドレスが5体登場。会場となったパリ市庁舎内のボールルームとの見事な調和を見せる。圧巻の美しさに、会場からは割れんばかりの拍手が起きたのだった。
ウジョー(Ujoh)


西崎暢と亜湖による「ウジョー」は、ブルース・ウェバーの初期作品としても知られる松田光弘によるブランド「ニコル(NICOLE)」の1983秋冬コレクションのカタログ「MEN&WOMEN」にインスパイアされた。身体を包み込むような贅沢な布使いに、ブランドが考えるラグジュアリーのヒントを見出したという。
コートやスーツ類は長くゆったりとしたシルエットで、ドレッシーな印象。裾から断ち出されたフリンジと共に、遊牧民の衣服のようなボリュームのある布使いは無国籍な雰囲気。スクエアに断ったドレープは、直線と曲線の融合を見せ、マスキュリン・フェミニンな印象を与えている。
モスグレー、エボニー、スチールグレー、グレージュなどの中間色を配し、差し色にトパーズ、ダスティーパープル、マルベリーをミックスして、コントラストを出している。スモーキングなどのフォーマルウェアに使用されるテキスタイルや、牝鹿の皮に似せて作られた厚地紡毛織物「ドスキン」と、対照的に艶のあるナイロンタフタを合わせて陰影を演出。
ケープのようなコートでスタートしたが、ゆったりしたシルエットの中に、完璧なまでの緻密な仕立てでストイックさを漂わせ、その緊張感は最終ルックまで途切れることがなかった。
取材・文:清水友顕/Text by Tomoaki SHIMIZU
画像:各ブランド提供(開催順に掲載)
>>>2024秋冬パリコレクション