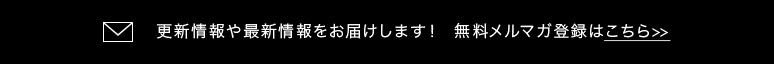PICK UP
2022.06.30
【2023春夏パリメンズ ハイライト2】トレンドがありそうでトレンドに左右されないのがパリ

写真左より「エルメス」「ロエベ」「セリーヌ」
先行のハイライト記事でも触れたように、今季は84ブランドが参加したが、それはウィメンズのパリコレクションに近い数である。しかし、ウィメンズよりも会期が2~3日短いため、1日が濃密となり、毎日が怒涛のようだった。特に後半はスケジュールが過密さを増し、大トリの「セリーヌ(CELINE)」が終わった直後は放心状態に。
メンズのパリコレクションの時期は、湿気が高く暑くなることもしばしばで、体力との勝負になりがちだが、今季は幸いなことに最高気温が25度以上になる日はほとんどなかった。それだけでも大いに助けられたのだった。
オーラリー(AURALEE)


岩井良太による「オーラリー」は、ピカソ美術館の中庭を会場にショーを開催した。今季はオフィシャル参加ではなく、独自にショーを行っている。
ゆったりしたシルエットでリラックスしたムード、という「オーラリー」のイメージを残しながら、今シーズンは落ち着いたトーンに明るい差し色を効果的に交え、そのコントラストが新鮮さを生み出していた。
オレンジのレイヤードドレス、パープルのニットプル、ブルーのブルゾンなどが、コレクション全体をオプティミスティックに見せている。トレンドカラーであるグリーンは様々なアイテムで見られ、フーディやバックスキンのつなぎ風ワンピースなどの他に、ユニセックスのシャツやバンダナにもあしらわれ、キーカラーともなっていた。
ボクサーショーツのギャザー部分をパンツの上からのぞかせたルックが数ルック見られ、またシースルーのウィメンズのブラウスやショーツ、ニットのブラトップが目を引き、さりげない艶っぽさを漂わせていた。
ロエベ(LOEWE)


ジョナサン・アンダーソンによる「ロエベ」は、パリ市のテニスコートを会場にショーを開催した。観客席に向かって下る、傾斜のあるランウェイは、モデルがウォーキングすると白バックとなる。背景に何も入り込まないため、ルックに集中出来るという革新的な構造となっていた。
自然とテクノロジーの共存をイメージし、そのコントラストを見せた。自然はチアとイヌハッカという植物に、テクノロジーは様々なイメージを映し出すデジタルスクリーンに象徴される。
植物の生えたコート、スウェットシャツ、スウェットパンツ、ランニングシューズはデザイナー、パウラ・ウラルギ・エスカローナとのコラボレーション。時間が経つにつれて作品が自然と融合していくというアイデアによるもので、植物を直接的に服に取り入れた斬新なアイデアに驚かされる。一方のデジタルスクリーンをあしらったコートやフェイスマスク、スウェットは、映し出される映像が服のモチーフとなるアイテム。
自然とテクノロジーという大きな題目を掲げながら、独自の手法でコレクションを構成し、「ロエベ」の革新性が更に大きく進んだ印象を与えた。
カラー(kolor)


阿部潤一による「カラー」は、パレ・ドゥ・トーキョーを会場にショーを開催した。ベーシックカラーと明るい色の対比は、これまでにこのブランドで幾度と見られたものだが、今季はその手法をより一層効果的に使用し、各ルックを新鮮なものに仕上げていた。
シンプルなジャケットとパンツには、全く異なる襟を重ねたアシメトリーのポロシャツやシャツをインナーに合わせ、その極端なコントラストが美しい。アウターについても、襟部分だけ全く違うアイテムから外して持って来たかのような大胆なものも多く見られたが、1つのルックとして見ると、緻密にバランスを計算してスタイリングされていることがわかる仕上がり。
レイヤードをしているようで、実はトロンプルイユ(だまし絵)的に袖や襟だけを重ねる手法は今季いくつかのブランドで見られたが、「カラー」の場合はポケットや襟の組み合わせ、ジップのチョイスなど、より一層複雑に作り込んでいる。しかし、複雑さの中にシンプルさも巧みに織り込んでいるため重々しくならず、全体に軽快さを漂わせている。
色と素材の合わせ、アイテム同士のコンビネーション。バランスの妙技を見せたコレクションだった。
マリーン セル(Marine Serre)


「マリーン セル」は、パリに隣接するヴァンヴ市ミシュレ高校の陸上トラックを会場に、大規模なショーを開催した。スポーツとファッションの融合を試みた今季は、マリーンが発表してきたアイデアを発展させたルックを随所に配している。
定番となっている三日月モチーフのレギンスやボディースは、依然として多くのルックに合わせられている。そして、これまでに見せてきたニットとレースをアップサイクルしたドレス、ヴィンテージのスカーフをあしらったワンピース、服飾史をなぞるかのようなシャネルジャケットを彷彿とさせるスーツなどが、マイナーチェンジを経て登場。その他に、ミリタリーウェアのポケット部分を繋ぎ合わせたコートや、Tシャツを解体してつなぎ合わせたドレスなど、アップサイクル作品も目を引いた。
これまでスポーティなアイテムは見られたが、今季はより直接的な表現をしたスポーツウェアが多かった。スイムウェア、トラックウェア、ボクサーショーツ、ボクサーガウンなどをモデルではない、リアルなアスリート達がまとって披露。
マリーソフィー・ウィルソンやクリステル・サン・ルイ・オーギュスタンなど、90年代に活躍したモデル達やジョルジャ・スミスなどのセレブリティも多数出演。最終ルックは、三日月モチーフのボディースをまとったマドンナの娘、ローデス・マリア・チッコーネ・レオンだった。
アンダーカバー(UNDERCOVER)


高橋盾による「アンダーカバー」は、ショールームにて最新コレクションを発表した。メインコレクション、高橋盾が日常着をイメージして作り上げたシェパード、そして「アンダーカバイズム(UNDERCOVERISM)」など、複数のラインを組み合わせて披露。
メインコレクションのタイトルは、ピンクフロイドの「狂気(The Dark Side of the Moon)」に因み、“The Dark Side of the Light Side”。グラフィック集団ヒプノシスが手掛けたピンクフロイドの代表作、「狂気」、「原子心母」、「炎~あなたがここにいてほしい~」、そして「アニマルズ」の4タイトルのアートワークを、スウェット、フーディ、ジャケットやブルゾンなどに落とし込み、巧みなアレンジを施している。
ドイツのエクスペリメンタル・ロックバンドのカン(Can)の曲から引用した歌詞をプリントしたTシャツや、黒澤明、小津安二郎、そしてサン・ラのポートレートをプリントしたTシャツも登場。羊のワッペンを縫い付けた日常着のシェパードは、和紙を用いたカーディガンやTシャツ型のニットなど、着やすさを追求したアイテムをラインナップ。「キジマタカユキ(KIJIMATAKAYUKI)」とのコラボレーションによるハット類も充実。
今季は装飾的にジップをあしらったジャケットやパンツが目立っていたが、「アンダーカバイズム」のラインでは、敢えて波打つようにジップを配したブルゾンが印象的。ブラジルの「メリッサ(melissa)」とのコラボレーションである、スタッズモチーフのサンダルを多くのルックに合わせている点も目を引いた。
エルメス(HERMÈS)


ヴェロニク・ニシャニアンによる「エルメス」は、18世紀に建てられた国立ゴブラン織工房の中庭を会場にショーを開催した。コレクション全体をバカンス、リゾート、海などのリラックスしたイメージで統一し、海の生物やボタニカルモチーフを織り交ぜて自然を意識させる内容となっている。
今季も象徴的なモチーフがいくつも見られた。コレクションを通して多用されたチェックについては、水面を上から覗いた時に見える動きのある曲線で描かれている。また馬をモチーフにしたスカーフプリントも同様に、水面を上から見た時に目に映る揺れを加え、新しい解釈のもとでシャツやポロシャツとして仕立てられていた。
サンセットモチーフのカシミアのタートルネックセーターとショートパンツでスタート。前半はショートパンツを合わせたルックが多く見られ、カジュアルでスポーティな印象。バリエーションで見せたブルゾンについては、ペガサスを刺繍し、4枚のスカーフプリント柄をそれぞれレザーや刺繍などのワッペンで表現し、ブローチのように縫い付けたものが目を引いた。また、服から落ちそうな位置に縫い付けられたポケット、あるいは斜めに縫い付けられたポケットを擁するブルゾンもユニーク。シルクカシミアのニットシャツも、有機的な水の動きを思わせる。またレザーのパッチワークトップスも、チェックモチーフが揺らめく曲線で表現され、水の動きを彷彿。インナーに合わせられたトップスや、レイヤーのように見えるトロンプルイユ(だまし絵)のパーカなどは、薄くて手触りの良いテクニカル素材で仕立てられ、やはり水の輝きが表現されている。
後半には、ボタニカルモチーフを打ち抜いて貼り合わせた素材によるジャケット類が登場。ドレッシーな印象を与えたが、ネオプレン素材のサンダルやスニーカーを合わせることでリゾート感は十分に保たれている。水にまつわる様々なイメージを服に落とし込みながら、バカンスのゆったりとした空気感も巧みに織り込み、モダンでフレッシュ、そしてエレガントなコレクションを創り上げていた。
ダブレット(doublet)


井野将之による「ダブレット」は、テュルゴー高校の中庭を会場にショーを開催した。コレクションタイトルは“IF YOU WANT IT”。プレスリリースには、4年前にシンガポールでフェイクスノーにはしゃぐ子供達の笑顔を目撃した時の光景に触れながら「ありえないようなことが起きる今の時代。ありえないような洋服で、ありえないようなファッションで。けれどそこに実際に存在すること。奇跡が起きることを信じて。世の中のどうにもならないことでも、がむしゃらに本気で思えば、きっと世界の少しでも変えることことが出来るはず。砂漠に雪を降らすように。 真夏のパリに雪を降らせることもきっと出来るはず。 少しでもあの時のような笑顔が広がるように」とするメッセージが書かれていた。
中庭には様々な役者たちがバーベキューをしたり、ピクニックをしたり、エクササイズをしたりと、それぞれの日常を演じ、ショーがスタートした途端に動きが止まり、モデルたちがその合間を縫ってウォーキング。
ピクセルをニットで表現したセットアップ、グローブと一体化したジャケット、髪の毛のようなフリンジのコート、筋肉のようなパンをプリントしたトロンプルイユ(だまし絵)的なTシャツなど、「ダブレット」らしい「有り得ない」シュールなルックが並ぶ。気付くと、薄い紙を細かくしたフェイクスノーが階上から降ってきた。一面が雪景色に。その中を、顔を真っ白にしてモデルたちが歩き、不思議な印象を与えた。
頭の出ない胴長のニットやジャケット、コートやジャージなど、「ダブレット」の真骨頂ともいえるルックが登場。両腕を寒そうにさするTシャツ姿のモデルが歩いてフィナーレへ。頭に積もった雪を模した紙を振り払いつつ、キツネにつままれたような、でも楽しい体験をした、という感覚が強く残ったのだった。
ナマチェコ(NAMACHEKO)


ディラン・ルーによる「ナマチェコ」は、デュペレ応用美術学校を会場にショーを開催した。
クルドにルーツを持つ二人は、今季クルドの民族衣装のエッセンスを所々に配し、全く新しい装いを提案している。クルド人の古い写真をプリントしたトップスやドレス、鈴を配したチェーンは直接的ではあるが、鈴の付いたチェーンは透明なボタンに変化し、ニットベストの飾りやシャツなど、様々なアイテムにあしらわれている。パンツやロングスリーブTシャツ、ショートコートやフーディ、レザーのライダースにまで縫い付けられ、ボタンの機能と装飾の役割を果たしていた。
今季は特に、ニットによるボディスーツをインナーに合わせるスタイリングが印象的。ジャケットとショートパンツのセットアップを重ねたり、ジャケットだけを羽織ったり、ムラ染めのトレンチとフーディを重ねたり、独特なレイヤードの手法を見せた。
キコ コスタディノフ(KIKO KOSTADINOV)


「キコ コスタディノフ」は、アンリ4世高校の図書室を会場にショーを開催した。ブルガリア出身のキコは、セントラル・セント・マーチンズ在学中からステューシーとのコラボレーションで注目を集め、2017年よりロンドンコレクションに参加。今年の3月にはパリでウィメンズコレクションを発表していた。メンズコレクションのパリ発表は今季が初。
両胸にくるみボタンを配したダブルブレストのジャケットと、バギーパンツのスーツでスタート。ピンストライプのライニングを表面に配したパンツやジャケット、そしてコートは丁寧な作りを見せる。異素材をパッチワークしたトップスとパンツのセットアップや、スタンドカラーのハーフコートなど、一見してシンプルだが、凝った作品が目を引く。
薄いコットン素材と厚みのあるパイル地を組み合わせたシャツやパーカは、そのコントラストの違和感が興味深い。
印象的だったのが、トレンドカラーであるグリーンのシリーズ。極端にダメージ加工されたニットを合わせたジャカード素材のスポーティなセットアップや、バックサイドから羽のようなパネルを配したブルゾン、六角のパーツをアップリケしたブルゾンなど、その独自性が際立っていた。
トム ブラウン(THOM BROWNE)


「トム ブラウン」は、コンコルド広場に面するオートモビル・クラブを会場にショーを開催。
冒頭でスーツ姿の数人のモデルが固まってウォーキングをし、突然音楽が聞こえなくなったと思ったら、何の前触れもなくマリサ・ベレンソン、ファリーダ・ケルファ、アン・ドゥオン、サーシャ・ピヴォヴァロヴァなど、60年代から現在までのスーパーモデル達が「トム ブラウン」のスーツをまとって登場。ショーが始まるまで最前列に空席が目立っていたが、それは演出だったことが判明。それぞれが席を見つけて着席し、ショーがスタートした。
女性の衣服のための織られた色とりどりのツイード素材を、様々な職業の男性の服に落とし込み、「トム ブラウン」による新たな解釈を加えて各ルックを制作。シェニール、デニム、グログラン、レザー、シアサッカー、チュール、レースなどを織り込んだツイードは南フランスの工房に特注されたもので、立体感のある重厚なファブリックはそれだけで強い存在感を示す。サーファー、船乗り、テニスプレーヤー、勤め人、パンクロッカーなど、様々な人々に合わせたコスチュームがランウェイを彩った。
後半は、アンダーウェアをきわどいラインで見せるショーツやミニスカートが多く合わせられ、やや挑発的な印象。マドンナの「Don’t Tell Me」がかかると、デニムツイードのコスチュームをまとった、半裸ともいえるカウボーイ姿のモデルが登場してポーズを決め、ビザールな世界を締めくくった。
セリーヌ(CELINE)


エディ・スリマンによる「セリーヌ」は、パレ・ドゥ・トーキョーを会場にショーを開催した。ブラックピンクのリサ、BTSのV、そしてパク・ボゴムの3人が来場するとの噂が駆け巡り、会場前には数千人単位のファンが押し寄せてカオス状態に。3人が会場に到着して姿を見せると、ロックコンサートさながらのどよめきが会場内にまで伝わった。
コレクションは、エディが得意とするグラマラスなロックテイストのルックで構成。70~80年代のムードや星条旗モチーフに象徴されるアメリカのイメージを巧みに挟み込み、クチュールのテクニックを駆使した華麗なアイテム群でコレクション全体を彩った。
エディが好むブラックタイは、今季は極端に細くなり、レザーのブルゾンとピンストライプのショーツに合わせられている。スパンコールを刺繍したニットカーディガンにはスローガンTシャツを合わせ、スウェットの上下にもスパンコールを刺繍し、カジュアルなアウターをよりゴージャスに、よりロック的に変換。ジャケット類はドロップショルダーのシルエットで、パンツはスリムに仕上げ、そのコントラストを強調している。
ゴールドパイソンのジャケットや、細かなパーツを組み合わせたクロコ風のネックレス、クロコを思わせるスパンコール刺繍のレザーのブルゾンなど、会場の天井から吊るされたゴールドのメタルモチーフのインスタレーションと呼応。爬虫類モチーフがコレクションのキーの一つとなっていることに気付かされたのだった。
今季目立っていたのは、何よりもグリーンという色だった。SDGsと直結する環境保全を想起させる色として、意識的か反無意識的であるかは知る由もないが、各ブランドはグリーンのアイテムを登場させていた。「マリーン セル」はアップサイクルされたTシャツやデッドストックのファブリックをわざわざグリーンに染めて使用。「キコ コスタディノフ」や「オーラリー」、「カラー」もキーカラーとしてのグリーンが目立っていた。「ルイ・ヴィトン」はコレクション後半に、グリーンを背景にした花咲き乱れる刺繍のシリーズを発表し、強い印象を残した。直接的にグリーンを取り入れたのが「ロエベ」。そのまま植物を服に植え付けるという大胆さだった。
モチーフとして目に付いたのがチェック。「リック・オウエンス(Rick Owens)」は大きい目のチェックをジャケットに取り入れ、「メゾン ミハラ ヤスヒロ(Maison MIHARA YASUHIRO)」はシャツやジャケットに、「ディオール (Dior)」はフーディやショートパンツにあしらった。「アンダーカバー」は、本場スコットランドのタータンチェック地を取り入れるというこだわりを見せていた。そのチェックをアーティスティックにアレンジしていたのが「エルメス」。水を通して見た時の揺らぎを加えて、有機的な曲線のチェックを考案した。「ケンゾー(KENZO)」も様々なチェックを使用していたが、ボーダーやストライプのバリエーションも豊かで目を楽しませた。ボーダーやストライプについては、「ルメール(LEMAIRE)」や「ドリス ヴァン ノッテン(DRIES VAN NOTEN)」、「ポール・スミス(Paul Smith)」や「セリーヌ」など、様々なブランドであしらわれていた。
アイテムとして目を引いたのが、重ね着(レイヤード)に見えるが、実は一つのアイテムになっているというトロンプルイユ(だまし絵)のフェイクレイヤードである。これはスケーターやバスケットボーラーなどのストリートスタイルからの引用。「ジバンシィ(GIVENCHY)」ではニットのスウェットとフーディをミックスしたトップスが、「アンダーカバー」ではフーディとTシャツを重ねたかのようなトップスが、「カラー」ではシャツを重ね着したかのようなトップスが登場。「エルメス」では、テクニカル素材による重ね着風フーディが見られ、ストリートスタイルとは異なるリゾート着としてアレンジしていた。
いくつかの共通項をピックアップしたが、しかしそれが全てではなく、主流でもない。各ブランドは各々の作風を打ち出しながら、それぞれのクリエーションを追求していた。全体的にカジュアル・ストリート志向になりつつある気はするものの、トレンドがありそうでトレンドに左右されないのがパリコレクション、というイメージは今季も崩れなかった。1月に開催予定の来シーズンはどうなるのか。外的要因・障害が多い現在、期待と不安が入り混じるが、静かにその到来を待ちたい。
取材・文:清水友顕(Text by Tomoaki Shimizu)
画像:各ブランド提供
2023春夏パリメンズコレクション