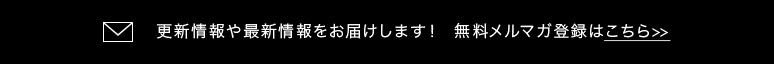PICK UP
2022.01.31
【2022春夏パリオートクチュール ハイライト】
ビッグメゾンはクラシカルが主流 気鋭デザイナーの前衛ルックも話題に

収束の兆候が一向に見えず、オートクチュール会期中には新規感染者数が50万人超との報道も流れたフランス。コロナ禍は依然として続いているが、果敢にもフィジカルなショーを開催するブランドが多かった。
今季、主催のクチュール組合が発表したカレンダー上には、29ブランドが掲載されたが、実に半数近くの14ブランドがフィジカルなショーを行ったのだった。これはファッションの回復傾向を示しているというよりも、実際に顧客を招いてショーを行わない限り、オートクチュールをビジネスとして成立させることが難しいという現実の表れではないだろうか。あるいは、実際にショーを行える潤沢な資金をバックにしたブランドだけが残っている状態、ともいえるのかもしれない。
昨年の参加ブランド数と比べると、今季は4ブランド減っている。増減に一喜一憂する必要は無いが、来シーズンも減る傾向であれば、この増減問題が懸念材料となる可能性はあるのだろう。
依然として五里霧中のパリファッションであるが、来シーズンの7月、あるいは来年の今頃までには完全復活していることを祈るばかりである。
アライア(ALAÏA)


ピーター・ミュリエによる「アライア」は、本社展示スペースにてフィジカルなショーを開催した。2017年に急逝したアズディン・アライアの後継者として、長年ラフ・シモンズの元でアシスタントを務めていたミュリエがアーティスティック・ディレクターに着任し、昨年の夏のクチュール会期中にプレタポルテコレクションを発表。今季は2シーズン目となる。
シルエットのキーとなるものがベルボトムで、レースのベルボトムが片足だけ付いたレオタードドレスや、ニットレースのベルボトムドレス、ホワイトシャツを合わせたデニムのベルボトムパンツなどが登場。大きなラフルを飾ったサイハイブーツを合わせたボディースーツは、まるでベルボトムをまとっているかのような錯覚を与える。
レザーパーツを爬虫類のように飾ったニットドレスや、リザードのベルトドレスなど、ボディコンシャスの代名詞的なデザイナーであったアライアのスタイルを継承。フェイスカバーのニットドレスは、アーティスティックなモチーフに彩られているが、これはピカソが1940年代に滞在していた陶器の産地であるヴァロリスでの陶器作品からの引用で、ピカソ財団とのコラボレーション作品。
その他にも、チェックのツイードのワンピースやコート、シマウマモチーフのロングコートドレスなど、生前のアライア作品からの引用が随所に見られた。
ディオール (Dior)


マリア・グラツィア・キウリが手掛ける「ディオール」は、ロダン美術館に設置された特設会場内でショーを開催した。インド人アーティストのマドヴィ&メヌ・パレクによる意匠を、前シーズン同様チャーナキヤ工芸学校とチャーナキヤ工房の職人達の手によって刺繍し、それらの作品を長さ92m、高さ13.5mの壮大な会場内に展示。豪奢な服と、プリミティブな雰囲気の刺繍作品とのコントラストが不思議な調和を生んでいた。
今季は特にテーマを設定せずに、高い技術力を持つアトリエとのコラボレーションによって生み出されるバリエーション豊かなアイテムを見せるという形式を取っている。特に今シーズンのシグネチャーとなっているのが、繊細な刺繍を施して立体感を出したタイツ。刺繍を施したコートドレスやスイムウェア風のボディースーツなど、様々なアイテムに合わせられ、シードビーズをループ状にフリンジにして刺繍したものやクリスタルとパールをビジュー刺繍したものが登場した。
刺繍を施したルックとシンプルな無地のルックが交互に登場し、シルエットとしては60年代のシンプルなフォルムを彷彿。亀甲のスパンコールを刺繍して銀糸で押さえたトップスや、短いバゲットビーズで四角形を全面に刺繍したドレスなど、刺繍のモチーフはシンプルだが高い技術力に裏打ちされたものばかり。「ディテール」に目を行かせるために敢えてフォルムはシンプルに抑えている。
アトリエが継承してきた高い技術をして、いかに女性を美しく装うか。オートクチュールの本質を追求する、並々ならぬ情熱を感じさせるコレクションとなっていた。
シャネル(CHANEL)


ヴィルジニー・ヴィアールによる「シャネル」は、2024年パリオリンピックに向けて改装中のグラン・パレに代わる展示会場として建設されたグラン・パレ・エフェメールにてショーを開催した。アーティストのグザヴィエ・ヴェイヤンがセットデザインをし、ミュージシャンのセバスチャン・テリエが音楽を担当。テリエは特別に作曲したトラックを演奏し、また第57回ヴェネツィアビエンナーレのフランスパビリオンにヴェイヤンが出品したクリスタルオルガン「クリスタルバシェ」を実演奏した。
冒頭、モナコのシャーロット王女が馬に跨って登場。複雑な形状のランウェイを巡って見事な馬さばきを見せ、最後はギャロップで走り抜けた。
コレクションは1920~30年代のアールデコ期の意匠、あるいはロシア構成主義の影響を随所に感じさせ、構築的なシルエットの中にこのブランドらしい繊細な刺繍やレースをあしらっている。
ノーカラーのツイードジャケットとパンツのシリーズからスタートし、ツイードのスーツは徐々に変形。インナーのワンピースにジャケットと共布のラップスカートを巻き付けるスタイルが目を引いた。スリットの要素はロングドレスでも応用され、レースに刺繍を施したロングドレスに深い切れ目を施している。
半円を重ねたようなジオメトリックなモチーフのシースルードレスは、ソニア・ドローネーの絵画を彷彿。透ける要素は多くのルックで見られ、バストから下のウエスト周りを透けさせたチュールのドレスのシリーズは、今季のキーとなるスタイルとなっていた。
ヴァレンティノ(VALENTINO)


ピエールパオロ・ピッチョーリによる「ヴァレンティノ」は、ヴァンドーム広場のショールームにてフィジカルなショーを開催した。コレクションタイトルは“Anatomy of Couture(クチュールの解剖学)”で、BGMは全編アノーニによる楽曲。
ビスチェ部分に深いカットを入れた、シンプルなミニドレスをまとったクリステン・マクメナミーでスタート。その他に、80~90年代に活躍したマリーソフィー・ウィルソンやヴィオレッタ・サンチェスなどを起用し、様々な年齢・人種のモデルで構成。また身体のサイズも様々で、それはあらゆる体型に合わせて服を作るオートクチュールそのものを体現し、今季のコレクションタイトルにも繋がってくる。
シャツドレスとボールガウンのセットアップ、ラウンドネックのトップスとスパンコール刺繍のマーメイドラインのスカート、あるいは微妙にスクエアなフォルムのピンクのノースリーブドレス。シンプルだが精緻、時にスポーティだが優雅でエレガント。ピエールパオロ・ピッチョーリが「ヴァレンティノ」で確立したスタイルは揺るがないが、今季はより一層洗練が進み、削ぎ落された美しさが際立っている。そして、様々なタイプの女性を賛美する内容となっていた。
今回はシャツルックから総刺繍のセットアップまで、11体のメンズも同時に発表された。
ジャンポール・ゴルチエ(JEAN PAUL GAULTIER)


前シーズンは「サカイ(sacai)」の阿部千登勢デザイナーをアーティスティック・ディレクターに迎えた「ジャンポール・ゴルチエ」。今季は「Y/プロジェクト(Y/PROJECT)」のグレン・マーティンスを選出し、本社パーティルームを舞台にフィジカルなショーを開催した。
グレン・マーティンスが「Y/プロジェクト」で見せてきた、歪みやひねりを加えたシュールレアリスティックな作風が、ゴルチエのアトリエの完璧ともいえる高い技術力と融合。あくまでもゴルチエらしさを維持しながら、奇抜で斬新なルックで構成されている。
前半はグラフィカルなジャカード素材によるトロンプルイユ(だまし絵)のスーツが登場。ウエスト部分のカットにより、肌が覗く作りがゴルチエらしく、またグレン・マーティンスらしくもある。コルセットを解体したロングドレスや、アランニットを再構成したロングドレス、マリンボーダーのニットにサンゴを刺繍したドレス、デニムリボンを編みこんだアランニットのドレスなどは、グレン・マーティンスでなかったら発想できなかったであろうアイテム。
後半のドレスのシリーズは圧巻。メタリックのアジサイを飾ったドレスや、雲のようにスカートが膨らんだメタリックグリーンタフタのドレス、ビスチェとタフタのスカートのセットアップなどは、これまでの「ジャンポール・ゴルチエ」の領域を超える、新しい美しさを示すルックとなっていた。
ヴィクター&ロルフ(Viktor&Rolf)


「ヴィクター&ロルフ」は、シャイヨー宮の舞踏室を会場にフィジカルなショーを行った。恐怖心を煽る不穏なBGMが流れる中で登場したのは、頭の高さ程に盛り上がったショルダーラインが特徴的なアイテム群。
不確実な現在の世界における恐怖の概念をポジティブなものに変換するために、美しいアイテムを提示する、という目的を掲げた今季。古いハリウッドのドラキュラ映画から引用されたタキシードやドレスは、再生可能な木材を原材料として生産されるテンセル™リュクスと他の素材をミックスして使用し、シューズブランド「メリッサ(Melissa)」とコラボレーションしたビーガンシューズが合わせられている。
モワレ織のロングコート、ブラウンのスーツ、花を刺繍したピンクのドレス、70年代風のボウタイ付きワンピース、ラフルを飾ったボールガウン。様々なルックが登場するも、肩の位置が高いだけで恐怖を覚えるのは不思議である。
そんな人々の心理を操りながら、現在の世界の状況を重ね合わせた上で、新しくて美しいものを生み出そうとする。「ヴィクター&ロルフ」らしいひねりの効いたインテリジェンスを感じずにはいられないコレクションとなっていた。
ユイマナカザト(YUIMA NAKAZATO)


中里唯馬による「ユイマナカザト」はプロテスタント教会のロラトワール・デュ・ルーブルにて2年振りにフィジカルなショーを発表した。コレクションタイトルは“LIMINAL(何かと何かの間にある、曖昧な領域)”で、インスピレーションの源泉となったものが、様々な神話に登場する想像上の生き物キメラ(Chimera)。「想像が現実へと変わる、その途中の曖昧な領域は、最先端の科学や先人の知恵などを結集し導き出される、人類がたどり着いていた最も先端の領域で、その領域こそが新しい価値観と可能性の象徴と捉えた」という。
着物袖のレースアップジャケットにパンツ、抽象的な極彩色のモチーフをあしらったレースアップのロングドレスなど、今季はモチーフアイテムが多かったが、これは中里が自主隔離をしている間に描いた絵を元にしている。多くは着物にあしらわれる、ミシンを使っての横振り刺繍を施した。メンズモデルも登場したが、ドレス=レディースという固定概念を崩し、特にジェンダーを問わない服作りを見せていたのが印象的だった。
これまでに使用してきたブリュード・プロテイン™(植物由来のバイオマスを主な原料とし、独自の微生物発酵によりつくられるタンパク質素材)の他に、天然由来素材をベースに制作し、ネームタグや品質表示含め、可能な限り枯渇資源である石油由来の素材の使用を減らしたという。中里の新しいことに挑戦する姿勢、様々な可能性を追求する姿勢を存分に伝える内容となっていた。
フェンディ(FENDI)


キム・ジョーンズによる「フェンディ」は、旧証券取引所を会場にフィジカルなショーを開催。ランウェイには、ローマの建築物のアウトラインを象ったオブジェを天井から吊り下げた。「フェンディ」の本拠地であるローマを「永遠の都ローマ、崇高なローマ、天国のごときローマ」とキム・ジョーンズは表現。優美な大理石模様や教会などの建築物といった歴史的側面に影響を受けながら、クラシカルモダンなドレスで構成している。
多くがロング&リーンなシルエットのドレスで、パンツルックはアストラカンのブルゾンとレザーのパンツを合わせた一体のみ。その他に、ミニ丈のドレスも見られたが、今季はミニ丈のスカートとロングのラップスカートを合わせたスタイルが目を引いた。ビスチェ風のミニ丈ドレスにオーガンザのロングスカートを合わせ、レッドとパープルのサテンのミニドレスにパープルのロングスカートを巻き付けて、視覚的な遊びを加えている。
彫像をハンドペイントしたベルベットのドレスやケープドレスも目を引いたが、ショー冒頭と最終パートで登場した白と赤のバリエーションの唐草モチーフのロングドレスは特に印象的。ファーとビーズと大きなパーツで丹念に唐草を表現し、その技巧の高さを示しつつ、トップ部分をタンクトップのフォルムにしてモダンに仕上げている、まさに今季の「フェンディ」を代表するようなクラシカルモダンな作品となっていた。
「ディオール」や「シャネル」といった老舗のオートクチュールブランド、あるいは後発組である「フェンディ」など、クラシカルなラインが印象的だった今季。刺繍を施すことで豪奢な雰囲気を醸し出しているが、洗練された手法がより一層各ルックをエレガントに見せていた。
一方の「ジャンポール・ゴルチエ」や「ヴィクター&ロルフ」は、人々を驚かしたり感情を揺さぶったりするような服作りをしていて、脳裏に焼き付いて離れない魅力を発していた。
「ジャンポール・ゴルチエ」で今季ゲストアーティスティック・ディレクターとなったグレン・マーティンスは、ゴルチエの作風を更に発展させた作品を考案し、その仕上がりには度肝を抜かれた。ここまで出来れば天晴であるが、それはゴルチエが培ってきたアトリエの技術力に支えられてのこと。クチュールの世界におけるゴルチエの存在感を思い知ることとなった。
また「ヴィクター&ロルフ」は、服が生み出す恐怖という負の感情と世界情勢を結び付ける作品作りをし、二人がこれまでに服を通して見せてきた知的作業の魅力が十分に伝わる内容となっていた。
今シーズンも一括りに出来るトレンドを語れなかったが、それぞれが目に麗しい、楽しいものであったことは間違いない。不穏な情勢の中で不安要因は多々あるものの、また来シーズンを楽しみに待ちたいと思う。
取材・文:清水友顕(Text by Tomoaki Shimizu)
2022春夏パリオートクチュールコレクション