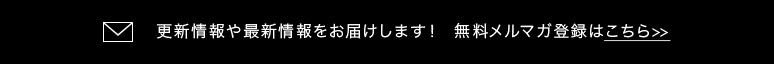PICK UP
2021.03.31
【宮田理江のランウェイ解読 Vol.72】ポストコロナ見据えて 強まる未来志向や文化ミックス 2021-22年秋冬東京コレクション

左から:ニサイ、フミト ガンリュウ、リコール
引き続きコロナ禍が影を落とした「楽天 ファッション ウィーク東京(Rakuten Fashion Week TOKYO)」だったが、クリエーションの冒険度が上がり、部分的ながら明るさが戻った。フィジカル(リアル)とオンラインでの発表に分かれたが、どちらも表現に工夫が凝らされた。冠スポンサーである楽天が日本発ブランドを支援するプロジェクト「by R」のショーでは「アンダーカバー(UNDERCOVER)」と「ビューティフル ピープル(BEAUTIFUL PEOPLE)」の2ブランドが開催。
クリエーション面では科学や未来のイメージを生かしたフューチャリスティックな切り口が現れ、ジェンダーを乗り越える表現が勢いを増した。ポストコロナの訪れを見据えて、おしゃれで遊ぶ感覚を大事にする、かつての「東京コレクション」らしさがゆるやかに復活。従来のやりかたにとらわれないデビューブランドの参加も東コレ全体の多様性を広げていた。
◆ニサイ(nisai)


松田直己デザイナーが「恋愛」をテーマに一点物の服を作るブランドだ。家庭用ミシンを買って、全くの独学で2015年にブランドを立ち上げたという異色のキャリア。ブランド初のランウェイショーでは「AFTER RAINBOW」を掲げて、メンズとウィメンズの混成コレクションを発表した。タイトルの通り、ブルーやレッド、イエロー、グリーンなど、明るい色が盛り込まれた。古着リメイク、アップサイクルを得意とするブランドとあって、大半のウエアがパッチワーク仕立て。ボロルックを思わせる、カラフルなつぎはぎが朗らかなムードを寄り添わせている。
抽象画家のパウル・クレーに通じる、色のリズムが楽しい。左右の丈違いやモチーフの食い違いもファニーな表情を生んだ。シルエットはレインポンチョにも似たオーバーサイズを多用。LGBTQ+のシンボルである虹ともつながりが深い色使いでジェンダーレスを感じさせた。古着の組み合わせ方にも、ミリタリー、ジャージー、デニム、ニットなど、元の素材ごとに異なる風合いを生かしている。楽観とウィットが交じり合い、色が元気感を上乗せ。モデルがスニーカーをペンキに浸してから登場し、ランウェイに足跡を残す演出も冴えた。
◆ミカゲシン(MIKAGE SHIN)


哲学者・ニーチェの手記をコラージュしたテキスタイルが知的なムードと弾むようなリズム感をまとわせた。ファッションに哲学が求められる中、「思考のプロセス」を表現したという試み。カリグラフィー的な手書き文字はアート感も高く、弾む筆致が装いにもパッションを添えた。アートや文学をヒントに、転換期の混沌と、新生の予感を表現。コンセプチュアルなアプローチは世界トレンドにもなじんでいる。京都の伝統工芸「墨流し」を生かした生地は流感を帯び、フリンジが装いに動きを宿らせた。
2019年にニューヨークでブランドを立ち上げた進美影デザイナーは建築的なデザインを取り入れたジェンダーレスウエアを提案している。トレンチコートは斜めに打ち合わせ、解体・再構成を試みた。プリーツスカートを多用して、テイストミックスに整えた。布を斜めに掛け垂らしたり、ジャケットの裾を片方だけウエストインしたりと、アシンメトリーで装いを演出。「個人の知性と強さを引き出す」という信条の通り、内なる強さを呼び覚ますかのように刺激的なルックを披露した。
◆リンシュウ(RYNSHU)


山地正倫周デザイナーが手掛けるブランド「リンシュウ(RYNSHU)」は前身のブランドから数えて35週年の節目。アニバーサリーにふさわしく、結婚式場「アニヴェルセル 表参道」を会場に、ショーをエレガントに演出した。長年にわたって、パリを発表の場に選んでいたが、2021年春夏シーズンから29年ぶりに東京でショーを開いている。引き続き、メンズが主体だが、ウィメンズも披露。ほとんどのモデルが大ぶりの黒サングラスを着用し、性別を越えたタフ感と凜々しさを印象づけた。
「ドレスコード」をテーマに据えた今回のコレクションで、来場者のドレスコードは「黒」。ショーでも黒系が主役に。白やオレンジを使ってコントラストを際立たせている。メタリック生地やつやめき素材でリッチ感も漂わせた。タキシードをキーピースに選んで、夜会服のようなムードを打ち出した。ドレッシーに整えながらも、キルティングやストレッチなど、機能的な素材・技法も交わらせている。ハンドメイドの花モチーフを肩や胸、ブーツに施して、程よいロマンティック感をプラス。パッチワークやファスナーでアクセントを添えた。バレエダンサーがモデルで登場して、リズミカルな動きでエレガンスを添えていた。
◆フミト ガンリュウ(FUMITO GANRYU)


パリコレに参加し続けてきたが、今回は東コレに初参加した丸龍文人氏はショーのインスタレーション演出に「リトゥンアフターワーズ(writtenafterwards)」の山縣良和氏を迎えた。6月にスタートする展覧会「ファッション イン ジャパン 1945-2020 流行と社会」との連動企画として新国立美術館でショーを開催。多様なモデルを起用し、アイドルグループ「BiSH」のメンバーもランウェイに登場した。ダッフルコートやコーチジャケットなど、オーバーサイズ気味のアウターが穏やかな輪郭を描く。
ボリュームたっぷりのファーハットやマフラー、パフィなキルティングアウター、カウチンセーターでコージーとドラマティックを融合。プレイフルなディテールも目立った。鎖骨あたりからエクステンション(付け髪)風なヘアピースを腰まで垂らす「人毛フリンジ」のディテールが目を惹く。ルックのどこかにQRコードをまぎれ込ませているのもウィットに富んだ細工だ。スウェットのセットアップは袖幅が過剰で、振り袖のよう。全体にジェンダーレスな提案が多く、多様性への目配りが行き届いていた。
◆アツシナカシマ(ATSUSHI NAKASHIMA)


ミラノ・ファッションウィークで発表を続けてきた「アツシナカシマ (ATSUSHI NAKASHIMA)」が約5年ぶりに東京でショーを開いた。テーマの「楚水」は曾祖父の名前。日本画家だった楚水の作品を服に写し込んで、墨絵系日本画のアートミックスに仕上げている。黒一色の元絵から多彩な色を引き出し、トレンチコートやMA-1、ワンピースなどを彩った。服をキャンバス代わりに、絵画作品を大胆に投影。モダンに蘇らせた。トレンドカラーに浮上してきたパープルやオレンジを生かし、グラデーションで動きを加えている。
着物ライクな右身頃と左のドレスをアシンメトリーにドッキング。着物風のカシュクールと、段々飾りのティアード袖が同居するといったカルチャーミックスが楽しい。着物とドレスとライダースジャケットの接合も試した。和花柄や虎モチーフなどがオリエンタルムードを濃くしている。着丈の長い羽織り物を重ねるレイヤードも繰り返し見せた。「FOREVER STRONG」の強いステートメントが躍る。デニムのセットアップにも楚水画を盛り込んで、タイムレスな和洋クロスオーバーに仕上げた。
◆ソワハ(sowaha)


「ソマルタ(SOMARTA)」で知られる廣川玉枝デザイナーが「新時代の和装」をコンセプトに、原宿デザインと共に立ち上げたブランドだ。今回の東コレがデビューショーとなった。日本文化の発信を行う文化的デザインプロジェクトと位置づける。キーアイテムは着物風の打ち合わせ「カシュクール」を生かしたワンピース。着物ライクなドレスだが、着付けを必要としない点でウエアラブルなアイテム。着物の雰囲気をデイリーに楽しみやすい、今のニーズになじむ提案だ。
日本の景色をデジタルプリントで写し込み、風景画を身にまとうよう。京都友禅染めの老舗「千總」「岡重」の協力を得て、幽玄の色調を帯びさせている。裾に向かって濃さを増すグラデーション「裾濃(すそご)」や、絵柄を描いた一枚布で仕立てる「絵羽模様」などの伝統技術がファンタジーを漂わせた。何枚もの襟が重なって見える「襲(かさね)」が重層的なレイヤードを演出。奥深い柄との相乗効果でエレガントな装いに導いている。
◆アデリー(ADELLY)


スタイリストの小松未季氏が2018年春夏シーズンからスタートしたブランドが東コレでのデビューを飾った。凛として華がある女性という意味が込められたブランド名にふさわしく、大人ロマンティックなワンピースを中心に、気持ちが浮き立つような装いを提案した。多彩な花柄をあしらって高揚感とフェミニンを薫らせている。透けるレースやオーガンジー生地、繊細な刺繍などを盛り込んで、あでやかさをまとう楽しさに誘った。
ボウタイやビッグリボンを多用して、気品と華やぎを同居させている。フリルやラッフルで、ボリュームを弾ませた。程よくふくらんだ袖は袖口で絞って、品格を演出。上品テイストと愛らしさをミックス。襟とカフスにアクセントを置いて、装いに動感を添えた。身頃と袖のカラーブロッキングもアクセントとなり、1枚で着映えするアイテムに。春夏シーズンのように軽やかな装いは、シーズンレスの着こなしが広がる時代にふさわしく映る。
◆バルムング(BALMUNG)


アウトドア気分と近未来感をねじり合わせたかのような異形のウエアを送り出したのはデザイナーのHachi氏。複雑に入り組んだ解体系レイヤードを軸に据えて、武装や登山ルックを思わせる重層的な装いを組み上げた。菱形のキルティングや、シャイニーなアルミ風素材を組み込んで、アウトドアやフューチャリスティックを思わせる。パズルのような重なり具合がプレイフルな雰囲気も漂わせていた。特大のバックパック、剣道の籠手(こて)風のロンググローブなど、量感が過剰で、宇宙服にも似たオーバーサイズ感を醸し出している。
端切れを3重に巻き付けたような不ぞろいのレイヤードがルックに動感を添える。ショートパンツには剣道の前垂れ状のパネルを重ねて、ウエスト周りに起伏をこしらえた。グレーをキーカラーに選び、白と黒を用いて、さめた無彩色のジェンダーレスコンビネーションがモダンなたたずまい。ポケットをいくつも付けたり、長い短冊風ピースを背中に垂らしたりと、ディテールのデコレーションに工夫を凝らし、好バランスを生んでいた。
◆リコール(Re:quaL≡)


最終日に迎えたのは、「ポストコロナ」を見据えた楽観や連帯のメッセージが感じ取れるポジティブなコレクションだ。ショーの幕開けでは、多様性を印象づける大勢のモデルが一斉に登場。床に座って自分たちのショーを観客のように眺めるという珍しい構成。ランウェイでもモデルたちの顔に笑顔がこぼれた。少年時代に見たアメリカンなプレッピーやヒッピーをミックスした「Refreppie(リフレッピー)」をテーマに掲げ、元気で伸びやかな装いを打ち出した。
ポンチョ風のアウターや、軍用フライトジャケットの変形版をキーピースに選んで、アクティブな着映えに整えた。フライトジャケットはキルティングライナー(裏地)を外出ししたり、シンボルのオレンジ裏地をのぞかせたりして、内外を交わらせた。フリンジ、バンダナ柄などのヒッピー風ディテールも多用。デニムのパッチワークも見せた。シグネチャー的なマルチ袖は歩くたびに袖が不規則に弾む。コロナ収束の願いと、遠くない未来への希望を込めたショー構成が会場全体をぬくもらせた。
創り手はコロナ禍の影響を受けながらも「ファッションの可能性」を押し広げた。アートミックスはアニメや日本画とのケミストリー(相性)を試し、着物や和工芸などのハンドクラフトとの融合も進んだ。サステナビリティーはもはや前提となり、様々な「大義」の発信が相次いだ。このような状況下だからこそ、装うことの意味を深く掘り下げたクリエイターたちは、着る人に寄り添いつつ、希望や元気をもたらそうと努めたようにみえた。
 |
宮田 理江(みやた・りえ)
複数のファッションブランドの販売員としてキャリアを積み、バイヤー、プレスを経験後、ファッションジャーナリストへ。新聞や雑誌、テレビ、ウェブなど、数々のメディアでコメント提供や記事執筆を手がける。 コレクションのリポート、トレンドの解説、スタイリングの提案、セレブリティ・有名人・ストリートの着こなし分析のほか、企業・商品ブランディング、広告、イベント出演、セミナーなどを幅広くこなす。著書にファッション指南本『おしゃれの近道』『もっとおしゃれの近道』(共に学研)がある。
|