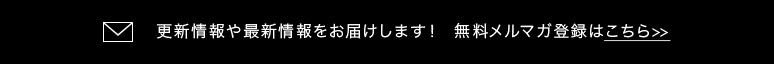PICK UP
2020.01.10
ゲストはmatohu デザイナーの堀畑裕之さんと関口真希子さん 第30回SMART USENの「ジュルナルクボッチのファッショントークサロン」

USEN(東京、田村公正社長)が運営する音楽情報アプリSMART USENで配信中の「ジュルナルクボッチのファッショントークサロン」。ウェブメディア「ジュルナルクボッチ」の編集長/杉野服飾大学特任教授の久保雅裕氏とフリーアナウンサーの石田紗英子氏が、ファッション業界で活躍するゲストを招き、普段はなかなか聞けない生の声をリスナーに届けるが、アパレルウェブでは、その模様をレポートとして一部紹介していく。第30回ゲストは「matohu」のデザイナー、堀畑裕之さん、関口真希子さん。
久保:今回は初めてのお二人ゲストです。「matohu(まとふ)」は日本全国の伝統的な技法などを活用し、モダナイズしてブランドに落とし込んでいるという、独特の位置にいます。ショーも何回か前から、ビデオで解説した後にモデルさんがプレゼンテーションするというスタイルに変えました。最初は「どうかな?」と思ったんですけど、すごく分かりやすくて心に入ってくる。コレクションブランドでも、ショーでは分からなかったけど展示会に行くと「凄いな、この素材」、といったことがあるんですよ。そういうブランドはやった方がいいんじゃないかって思わされる新しいやり方、試みをしているブランドです。
石田:では、まとふのデザイナー、堀畑裕之さん、関口真希子さんです。
堀畑・関口:こんにちは。
石田:いやあ、佇まいが上品ですね、お二人とも。
久保:「はんなり」みたいな感じ?
石田:聡明な哲学者というようなイメージです。
久保:大学は哲学科ですよね、堀畑さん。
堀畑:大学と大学院で哲学をやってからこの仕事に入ったので、ちょっと他のデザイナーさんとは毛色が違うのかなとは思います。
久保:カントを勉強されていた? 『純粋理性批判』でしたか。僕も大学時代に一応、読みましたけど……。文庫で3冊くらいでしたっけ?
堀畑:岩波文庫で。大学に入った頃は1ページも読めなかったですね。お経を読んでいるみたいな感じでした。でも、カントの中には哲学の問題が全部詰まっているんですよ。『純粋理性批判』を1冊勉強すると、哲学的な問題は全て頭に入るかなとは思います。
<中略・堀畑さんの出身地・大阪の話>
石田:お父様、お母様は服飾関係のお仕事をなさっていたのでしょうか?
堀畑:父は堺で倉庫とか物流の仕事や梱包の資材の製造の仕事をしています。母は東京にある現在の杉野服飾大学を出ていて……。杉野芳子さんに直接習っていたんです。
久保:初期の杉野で学ばれていたんですね。
堀畑:本当は服飾の仕事をしたかったんじゃないかな。家にもミシンがあって、よくいろんなものを作ってくれました。
石田:やっぱりDNAを受け継いでいらっしゃったんですね。で、大学は同志社で哲学を専攻された。
堀畑:自分がどうやってこれから生きていけばいいのか。人はいかに生きるべきか。人生の真理を知りたいという思いがあったんです。せっかく4年間学べるんだったら、人生に役立つようなことを学びたいと思って哲学科に行きました。
石田:そこからファッションへ……。
堀畑:そこの飛躍が、ね。みんなは「大丈夫か?」みたいな。いきなりファッションとか言い始めたので、哲学をやり過ぎて頭が変になったんじゃないかって言われました。
石田:関口さんはどちらのご出身なのですか?
関口:東京なんですけど、生まれたのは実は大阪。たまたま母が私を産んだのが大阪の病院でした。生まれただけなんです、大阪は(笑)。育ちは東京です。
石田:ご両親は服飾関係?
関口:父は国家公務員です。母は専業主婦だったんですけど、物作りが好きな人でした。私には妹がいるんですけど、子どもの頃からよくお揃いで服を作ってくれましたね。そういうことがわりとあったので、手で何かを作っていくという感覚は身近でした。布を一緒に見に行って、「これでスカートが欲しいな」とか。日常的なものというよりは、どこどこに出かけるときのために二人にお揃いでワンピースを作ろうかとか、そういう感じでしたね。
石田:大学時代は法律を学ばれていたとか。
関口:憲法ですね。私が学んだ憲法は哲学的というか、どちらかと言うと思想の方だったので、カントも読みました。『純粋理性批判』は歯が立たないと思って、『道徳形而上学原論』でしたけど。だから、その後に入った文化服装学院で堀畑と会ったときには、何となく親しみが湧いたというか。「この人とはお友達にならなくちゃいけない」って感じでしたね。大学時代はそのまま大学院に行って研究とかできたらいいなと思っていたんですけど、あるとき服を……。

石田:関口さんも!?
関口:デザイナーになりたいとは全く思っていなくて、自分で着たいものを作りたいなと思ったのです。本を見て、パターンを引いて。ただ、それだけだと限界があるから、専門学校のことはあまり考えたことはなかったのですが、「服って勉強できるんだ」って気がついて。大学は自分が学びたいことをどういうふうにしたら学べるのかを身につける場所、自分が学びたければこれからも学んでいくことはできる。でも服は今、勉強しないと作れない。両親には大学院に行くと言っていたけれど、専門学校に行かせてくださいと頼んだのです。すると「それで食べていくんだな」と言われたので、「自分の仕事としてやっていきます」と宣言しました。背水の陣でしたね。
久保:堀畑さんがファッションに目覚めたのは、いつ頃のことですか?
堀畑:大学院時代です。哲学者の鷲田清一さんが当時、ファッションを哲学的に読み解く著作をたくさん出されていたんですね。たまたま本屋で手に取って、ぱらぱらと読んで、ファッションって単に流行のものと思っていたけど、人間のあり方とか、生きていく上での大切な要素としてあるということに気がついたんです。
久保:そこまでは知らなかった?
堀畑:全然知らない、普通の大学生でしたから。お洒落も古着とかそういう感じでしたから。パリコレなんて「火星の盆踊り」くらいな感じで。
久保:火星の盆踊り(笑)! いい表現だなあ。年4回やってますよ、火星の盆踊り(笑)。
堀畑:そういうのに初めて触れて、クリエーションに鳥肌が立つほど感動したんです。展覧会やテレビの『ファッション通信』も観て、こういう世界があるんだと、すごく惹かれていきました。デザインができるかどうか、服が作れるかどうかなんてどうでもよくて。自分が心震える世界に飛び込んでみたいという、それだけのがむしゃらな思いでした。針すら持ったことがないのに、自分はこの仕事をやろうと、朝日が昇ってくるのを見ながらジョギングをしているときに決意したんです。デザイナーになるか、パタンナーになるか、営業になるか、何になるかは分からないまま。とにかくクリエイティブな会社の一員になって仕事をして、手に職をつけて、自分の足で立って生きていこうという決意でした。とはいえ、哲学を諦めたわけではなかったので、物事を深く考えて何かを問いかけていくということを仕事としてやりたいと思って、そこに向かって行った感じです。何が何でもファッションというよりは、人が装うということの意味を深く問いかける仕事がしたかったのです。
久保:それでお二人は同級生として出会うわけですね。
堀畑:最初のクラスで、最初に会ったクラスメートに話しかけたんです。
関口:そのときに自己紹介みたいなものがあったんですけど、本当に何もモノを作ったことがない人がモノを作ることを学ぶ学校に来るんだなと思って。「並縫いをします」って言われても、並縫いっていう言葉を知らない。あっ、この人、すごいなと(笑)。
<中略・ヨウジヤマモト、コムデギャルソン時代の話、物作りにおける言葉の大切さの話>


石田:お二人それぞれに研鑽を積まれて、そして一緒にブランドを立ち上げたのでしょうか。
堀畑:会社に5年間勤めて、自分たちで何かをやってみたいと思ったんですね。まだ誰もやっていないことがあるんだったらやりたい。でも、そうではなくて、自分がいる会社に毛が生えたようなものを作るんだったら、やらないほうがいいと思っていました。
関口:最初から自分たちでブランドをやりたいとは思っていなくて、クリエイティブな物作りに関わっていきたいという意識だったんです。
堀畑:何かあれば自分たちでもやってみたい、それが見つかるまでに5年かかったということです。見つかるきっかけが「着物」でした。関口は着物を着ることが趣味で、週末によく着ていたんですね。で、あるとき、頼んでもいないのに、古着屋で僕の分の着物を買ってきて、一緒に着ようという話になって……。「えっ!?」と思ったのですが、それで着物っていうものを何でもない週末に着るようになったのです。でも、男性で着物を着ている人って少ないでしょ? 歩いているとじろじろ見られるんですね。街の中にいると自分が異物になったような気がするんですよ。日本人が何百年も着てきたものを、今、東京で着て歩いていると外国人みたいに見られる。「これって何?」と。日本のファッションが歩んできた歴史を改めて鳥の目線で見る瞬間が訪れたんですね。なぜ日本人は着物を着なくなってしまったのか。着物を着なくなって失われていった美学とか、着物の中でしか表現できないあり方というものがあったはずだろうと思ったのです。そういうものを忘れてしまっていると。


関口:その辺のことは、着物を着るときにはまだかろうじて感じられるんです。例えば色合わせも、女性だったら赤とか青とか紫とかを合わせることができたり。そういう感覚って、着物を着る時にはあるけど、日常の服を着る時とは使い分けているじゃないですか。もったいないなと思ったんですね。
石田:それでロンドンに渡り、日本とは違う環境でコンセプトを築き上げ、日本に戻って来て、まとふを立ち上げられた。
堀畑:戻って来たときには迷いなく「こういうことをやろう」と決めてスタートしました。そこの部分はずっとブレないでやってきているのかなと思います。
久保:今は青森のこぎん刺しや徳島の藍など、日本の伝統的な物作りにコミットしています。
堀畑:そこにたどり着くまでに結構、時間がかかっているんです。ブランドをスタートして5年間・10シーズンは「慶長」をテーマにしました。学びの時期だったのかもしれません。桃山時代の終わりから江戸の初めの美術工芸、風俗には非常に面白いものがあって、日本のルネサンスみたいな時代で、すごくエネルギッシュなんですよ。そこにインスパイアされて、織部焼を服にしたり、かぶき者をテーマにしたり、南蛮人をテーマにしたり。ファッションの文脈とは違う、何が流行って、どういったマーケティングで売るかというのとは全然違う表現に取り組みました。その後、「日本の眼」というタイトルで、日本人が歴史の中で培ってきた美意識を服にしたのです。例えば「うつり」「みたて」「つくし」といった言葉だけでは分からない美意識を題材に、8年間で17コレクション。そして今、改めて日本の工芸・民芸の世界とつながる物作りをしています。その場に自分たちも身体ごと行って、感じて、その土地の自然、モノを作っている人たち、あるいは食べ物とか、いろんなものを取材しながら服を作っています。そのテーマが「手のひらの旅」です。人間の文化を作り出してきたのは、手のひらなんですね。道具も、衣服も、建築も、食も、全て手から生まれています。この「手」という原点に帰って、手仕事を見つけに行って、一緒に物作りをする。グローバル化の中で、そこに行かないと手に入らないものの重要性がすごく際立ってきていると思うんです。そういうことをコレクションでやっていきたいと考えています。
詳細は、SMART USENでお聴きください。
▼公開情報
USENの音楽情報サイト「encore(アンコール)」
http://e.usen.com/