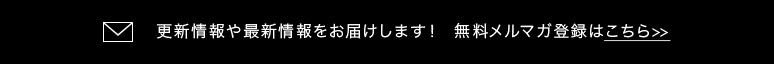PICK UP
2019.07.12
ゲストはユナイテッドアローズ上級顧問の栗野宏文さん 第24回SMART USENの「ジュルナルクボッチのファッショントークサロン」

USEN(東京、田村公正社長)が運営する音楽情報アプリSMART USENで配信中の「ジュルナルクボッチのファッショントークサロン」。ウェブメディア「ジュルナルクボッチ」の編集長/杉野服飾大学特任教授の久保雅裕氏とフリーアナウンサーの石田紗英子氏が、ファッション業界で活躍するゲストを招き、普段はなかなか聞けない生の声をリスナーに届けるが、アパレルウェブでは、その模様をレポートとして一部紹介していく。第24回のゲストは株式会社ユナイテッドアローズの上級顧問、栗野宏文氏。

<前略・オープニングトーク>
石田:今日は栗野さんがどんな人生を歩んで来られたのか、伺ってまいりたいと思います。まずは生い立ちから。
栗野:前世紀にこの世に生まれて、前世紀からこの仕事をしています。僕は父親の仕事の都合で、1953年にニューヨークで生まれました。1年くらいしかいなかったので、記憶は全く無いです。空気を吸っただけ。日本に帰ってきて、今では帰国子女はわりともてはやされるけど、当時は逆で、いじめられました。戦後はまだ終わっていないというか、「お前なんかアメリカの味方だろ」みたいなことを言われたり。その後は2年くらいオーストリアに行ったんですけど、そこでも石を投げられたり……。それがトラウマということでは全くないんですけど、今振り返ると、そういう経験をしたことで、「逆にそういうことはいけないな」って早い時期に理解できました。その意味では良かったんだと思っています。
でも、海外に行っていたと言うと、「ちょっと違うやつ」的な目で見られてしまう。だからずっと言わなかったんです。この業界に入ってからもニューヨークで生まれたとか言うと、絶対に「だからなのか」とか言われるから。ずっと東京出身って言っていました。でも、ダブル略歴みたいなのは嘘っぽくて良くないというので、1回ちゃんと本当のことを言おうと思って、近年は正直に言っています。
久保:なるほど。でも、小学校時代にオーストリアから帰ってきて、周りからは「あいつ、海外に行ってた奴だぞ」みたいな目で見られたってことですもんね。
栗野:残念ながらね。やっぱり人間っていうのは自分と異なるものに対して、本当は仲良くなりたいという部分と、なんだかよく分からないという部分があるんですよね。だから「違う」ということに対して人はもっとポジティブにならなきゃいけないなって、やがて思うわけです。
久保:でも、ちょっと不寛容さを感じたということですか。
栗野:そうですね、イントレランス。それで、自分がファッションの仕事をするようになってからは、ますます「多様性」とか「違う」ということが価値だと思ったのです。ああいう経験をしたというのは100%マイナスじゃないんだということは思います。
洋服に興味を持ったのは母親が関係しています。私の母親はすごく映画好きで、小学校の頃からよく映画館に連れて行ってもらっていました。子どもが喜びそうな西部劇とか、もうちょい大人っぽい映画にも連れ行ってくれました。そうすると、映画を通して俳優が着ている服とかに目覚めてくわけですよ。「あなたにとっておしゃれの原点はなんですか?」みたいなことを言われると、母親に連れて行ってもらった映画だと思いますね。
<中略・イラスト、イコノグラフィーに傾倒した学生時代>

久保:ロックはどういうものが好きだったのですか?
栗野:最初は小学校5年の頃。サーフィンミュージックが好きになったのです。「ベンチャーズ」よりちょっとマイナーな「アストロノウツ」というバンドがあって、同じ『パイプライン』という曲をやっているんですね。テケテケテケっていう。あれが生まれて初めて自分のお小遣いで買ったレコードです。その後、ビートルズを知りました。66年に来日した彼らをテレビで観て、「すごいな」と。それで髪を伸ばしたり、制服を着なかったりというようになっていったのです。当然、学校とはもめますよね。別に不良のつもりはなくても、髪は長い、制服を着ない、ズボンは細いというだけで悪者扱い。そこで、締め付ける側は自分をどういうふうに締め付けようとしているのか、それに対して自分はどういうふうに生きていったらいいのかを、否応なしに学ぶわけです。そこが自分の出発点ですね。
久保:その時は屈せざるを得なかった?
栗野:屈したのか、屈していなかったのか。結局、髪も切っていないし、制服も着ていませんでした。無視していたのですかね。
久保:よく卒業できましたね。成績が良かった?
栗野:音楽や美術は一番良い成績で、国語も英語も良くて、でも数学と物理はダメ、体育もダメみたいな。でも偏差値システムだから、英語、国語、美術、音楽が良かったりすると、全体としては結構良い感じになるんですよ。
久保:問題ないってことで(笑)。
栗野:まぁまぁ。で、都立高校に入って、一浪して大学に入って。大学ではイコノロジーとかイコノグラフィーとか、もうちょっとややこしいジャンルの記号論を勉強しました。
石田:その時は何を目指していたのですか?
栗野:何ひとつとして食べていけないものでしたね。学者になるわけでもないし、物を作っていないからアーティストにもなれないし。友達には映画を作っている人やミュージシャン、脚本を書こうとしている人もいました。その中で自分は強いて言えば、「生きているだけでクリエイティブであったり、在り方そのものがクリエイションになるような人になれたらいいなあ」と思っていました。何かを目指すとか何かの職業ではないんですね。幸いファッション業界に知り合いがいて詳しく説明してもくれたので、映画や音楽の次くらいにファッションに興味があった結果、この世界に行こうと決めたのです。77年に入って、もう42年もやっています。
石田:鈴屋に就職されたんですよね?
栗野:そうです。今はもうない会社で、残念ですけど。当時は日本で一番大きいファッション小売りの会社で、パリや香港、ニューヨークにもお店がありました。僕が入った時はピッカピカというよりは、「ちょっと大きくなり過ぎているんじゃないか」というニュアンスがありましたけど。新卒で入って上野の本店に配属されて販売をやったのですが、上司は厳しい人ばかりで、すごく厳しく育てられました。そこで小売りのベースを叩き込まれたのです。タイムカードなんかあってないようなもので(笑)、1年半くらいやって、「これだけ働いたら怖いもの無し」みたいな勢いでそのままきちゃったというか。
久保:鈴屋の後にビームスへ?
栗野:鈴屋を辞めて数カ月間は何もしていなかったんです。失業保険をもらって、これで映画を観ようと……。人生でここまで暇な時はないだろう。だから「映画のためならどこでも行くぞ」と。家は世田谷だったのですが、関東近県で面白い映画をやっていればどこへでも行って映画を観ていました。だけど、だんだん資金も無くなってきて……。そうこうするうちに「ビームスっていう面白いところがあるんだけど行ってみない?」と紹介してくださった方がいたのです。それでビームスに入って、再び洋服屋人生が始まりました。
<中略・鈴屋時代、ビームス時代、お天道様は見ている的な商売の話>



久保:栗野さんは洋服に関するいろんな知識や背景をご存知じゃないですか。男性はどちらかというと、そうしたうんちくに惹かれて買う部分があります。それ以外にも、例えば映画や音楽など興味をそそるような話題がありますが、そういう部分は接客時の話として広げていくものなのですか。
栗野:ユナイテッドアローズはどちらかというとそっちですね。商品知識はもちろん大事ですけど、「知識」というのは本を読めば誰でも得られるじゃないですか。一方、「知恵」はオリジナルですよね。商品知識やうんちくを武器にすることもできるけれども、本当にその人にとってクオリティー化されるものは、知識が骨肉化されて言語化され、その人のオリジナルになってアウトプットされたもの、つまり知恵じゃないかと思うのです。
久保:なるほど。知識を得ることはとても大切だけれども、それを自分の言葉で喋れるようになること。自分のものにして語れるということが重要であると。
栗野:それも相手にとって受け入れられやすいように。知識はややもすると相手にとってトゥーマッチだったり、「そういうのやめてよ」「それ知ってるよ」ということもありますよね。そうなると物知り合戦みたいになって、楽しくはない。それよりは「そういう工夫があるんですか」みたいに相手の話を傾聴するほうがいい関係を構築できる。それが知恵なんでしょうね。
<中略・海外の大学・アワードでの審査員経験、ユナイテッドアローズ創業の経緯>
久保:ユナイテッドアローズを1989年に創業した時、「新しい日本のスタンダードを創る」という旗印を掲げました。今年で30年、実現できましたか?
栗野:まだ全然できてないですけども、それを言い続けてきたのは良かったと思っています。我々が「新しい日本のスタンダードを創ろう」と考えたのは、一つの例として、当時の日本のサラリーマンがソフトスーツと呼ばれたイタリア調のスーツを着ていて似つかわしく無かった、という状況がありました。
久保:「六本木スーツ」なんて呼ばれていましたね(笑)。
栗野:ジョルジョ・アルマーニをチープに解釈したような、肩幅さえ広ければいいみたいな。「それを普通に堅気の人が着ちゃまずいだろ、元ネタのアルマーニにも失礼だろ」みたいなものでした。「これが日本のスタンダードじゃまずいんじゃない?」という強い思いがあったのです。ならば、「世界のどこへ出ても恥ずかしくないようなスーツの形を提案したい」ということがあって。それはやがて新しいタイプのトラディショナルとして、ほぼ日本のビジネスマンのスーツの基本的な形にはなりました。
洋服以外にも、和食器やお箸、茶筒を売ったりしてきました。それは、生活の隅から隅までクオリティー・オブ・ライフを楽しんでもらいたいという思いの一つの表れです。今、そういう意味でのジャパニーズスタンダードはある程度、皆さんが体験されたと思うんですね。次に考えるのは「多様性」です。人間の多様性、あるいは日本と他の国との支え合いみたいなものにどうコミットメントしていくか。ユナイテッドアローズがこの5年くらい取り組んでいる次なるスタンダードづくりは、そっちに向かっています。
石田:最後に、ファッション業界を目指す方にメッセージを頂戴できますでしょうか。
栗野:自分が親から言われたように、自由に生きなさい、と思っています。その代わり、責任を取ろうよと。自分自身が仕事をしてきてすごく学んだことは、直感と勉強の大切さです。何かを良いと思ったら自分の直感を信じる。その代わり、なぜ良いと思ったのか裏付けを取る努力もする。勉強だけをしていると勉強バカになって、知識だけになってしまいます。直感だけを信じていると、ドン・キホーテ状態になって、風車に突進していく人になってしまいます。直感的にピンと来るものがあったら、その裏付けを取りに行く、その両方をうまくやると成長できると思うのです。たぶん人類の歴史は、「間違いを犯すこと」と「直感を信じること」の繰り返しだったのかなと思いますね。
<後略・クロージングトーク>

詳細は、SMART USENでお聴きください。
・SMART USENの「ジュルナルクボッチのファッショントークサロン」、第24回のゲストは株式会社ユナイテッドアローズ 上級顧問 栗野宏文さん
▼公開情報
USENの音楽情報サイト「encore(アンコール)」
http://e.usen.com/