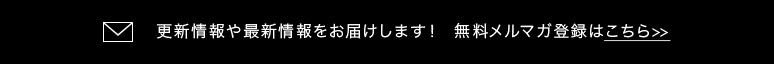PICK UP
2025.10.13
【2026春夏パリハイライト3】個性が生む「服の力」― 前衛や気鋭デザイナーたちの現在地

写真左から「ヨウジヤマモト」「イッセイミヤケ」「リック・オウエンス」「トム ブラウン」
服を一見しただけで、ブランド名やデザイナーの名前を言い当てることの出来る場合がある。特に、パリコレクションに参加するデザイナーの服について、それが当てはまるのかもしれない。唯一無二の世界観を打ち出すことで、デザイナーやブランドの評価・価値を高めて行くという流れがパリにはあり、それが服に強さをまとわせているのではないだろうか。パリコレクション第3回目のハイライト記事では、そんな強い個性を放つ、時にアヴァンギャルドと評されるデザイナーたちによるコレクションを紹介したい。また、「トリシェジュ(TORISHÉJU)」や「ジュリ ケーゲル(Julie Kegels)」など、注目の新進デザイナーによるコレクションも併せて紹介する。
ヨウジヤマモト(Yohji Yamamoto)


これまで通り、パリ市庁舎の舞踏会用広間でショーを開催した「ヨウジヤマモト」。「千と千尋の神隠し」の主題歌「いつも何度でも」や「天空の城ラピュタ」の主題歌「君をのせて」のカバー、あるいは山本耀司本人による「千の風になって」などをBGMに登場したのは、装飾的なドレスの数々。しかし、コントラストを描くようにシンプルなドレスも見られ、カラーパレットも今季はバリエーション豊か。多くの黒に対して白や赤、ブルーを配していた。
糸を抜いてフリンジに仕立てたドレスや、襟や袖元を思わせるパーツを縦横無尽に配したドレス、太いコードで編んだイレギュラーなニットを配したドレス、プリーツを掛けたチェックをあしらったドレスなど、今季を象徴するドレスのシリーズが印象的。所々千切れたレースを飾ったドレスは、アンティークのような効果を見せていた。
途中、パオロ・ロヴェルシが撮影したジョルジオ・アルマーニのキャンペーンフォトをプリントした追悼作品のドレス2点が登場。1点には、今年9月28日に開催された50周年記念ショーに山本耀司を招くためにアルマーニが書いた、個人的な手紙がフロント部分にプリントされていた。
今季も「LIMI feu(リミ フゥ)」の作品がコレクションに組み込まれている。ミシン掛けしたフリンジのドレス、ドレーピングが美しいモノクロのドレス、共布で作成したコードをスリーブに配したドレス、ドレープを中央に集めて編み込んだかのようなロングドレスの4点。それぞれ手作業の確かさと造形の美しさを見せ、強く印象に残る作品となっていた。
赤いコートを合わせた4ルックと、トレーンを引くオーガンジー製の赤いバスルを合わせたルックでショーは終了。様々な要素が絡み合う、これまで以上にドラマティックなコレクションとなっていた。
イッセイ ミヤケ(ISSEY MIYAKE)


© ISSEY MIYAKE INC./Photo by Frédérique Dumoulin-Bonnet
近藤悟史による「イッセイミヤケ」は、改装工事中のポンピドーセンター内でショーを開催。コレクションタイトルを“Being Garments, Being Sentient”とし、「衣服は意識を持つのだろうか」という問いから服作りをスタート。衣服にまつわる既成概念を取り払い、そこにあるはずのないものを着想源とする。意識を持つ、生き物としての新しい「衣服像」を描いたという。
フォルムを固定する骨組みを内蔵したルックでスタート。服が生長して脱皮していく姿を描いている。有り得ない場所に袖が付いているパンツや、片腕を出せる構造のジャケットなどは、自由な着方を選択できる遊び心あるアイテム。
シューズが衣服に取り込まれたシリーズは、「カンペール(Camper)」とのコラボレーションによるもの。靴が増殖して一体化する様を表現。収縮性のある薄いジャージーをあしらったシリーズは、洗剤のボトルなどを収められるようにデザインされ、消費社会の縮図を見せる。
シャツのパターンを内蔵し、ジャケットの下にシャツを着ているように見えるリバーシブルジャケットのシリーズ、1枚の布からドレープを寄せて完成させたワンピースのシリーズに続き、URBAN JUNGLEのシリーズへ。ヤシ科の植物をフォトプリントしたドレスの他に、葉の形状を模したプリーツドレスが登場した。穴を開けることで、様々な着こなしが出来るニットのシリーズも興味深い。
ショーでは、溢れんばかりのアイデアによるアイテムが矢継ぎ早に登場。衣服が意識を持ったらどうなるのか、というイマジネーションの世界をこのブランドらしい手法で描き切っていた。
リック・オウエンス(Rick Owens)


Courtesy of Rick Owens/Photo by OWENSCORP
パレ・ドゥ・トーキョーの噴水を舞台にショーを開催した「リック・オウエンス」。今年6月に発表されたメンズコレクションからの流れを汲み、タイトルを“Temple of love”と題し、硬軟の素材を組み合わせる独自のレイヤードを提案した。
今季は、大きな肩のラインが特徴的。血管をイメージしたというチュールのトップスには、更にチュールのドレスを重ね、その上からロボットを思わせるフェンダーと呼ばれる樹脂製のショルダーを載せる。また、タンクトップ型のロングドレスには、肩から袖に掛けてサイドに飛び出したようなチュール製トップスが合わせられていた。
ドラキュラカラーのブルゾンやヴィクトール・クラヴェリーとのコラボレーションによるレザーニット、ニューヨークのスーサイドとのコラボレーションブルゾンもメンズコレクションから継続。リック・オウエンスが誕生した時に父親が作成したという星座表プリントも再登場し、今季はシルクとチュールのボンバースやロングドレスにあしらわれている。
今季は、「リヴィ(Livy)」とのコラボレーションによる、直線的なラインで構成されるブラとショーツも発表。レイヤードのアクセントとなっていた。
トム ブラウン(THOM BROWNE)


宇宙人が地球を侵略するという奇想天外なストーリーを思い描き、エイリアンに襲われた人間の様子を服に落とし込んだ「トム ブラウン」。
袖が8本のジャケットと脚が6本のパンツをまとったエイリアンで幕開け。テーラードの新解釈は続き、プレッピー風のセットアップは、実は一体成型のドレスで、鎧のような猛烈な重厚さを持つアイテム。ペインティングモチーフをスパンコールで刺繍したトップスは、エイリアンに襲われた人間の身体を表現。
今季はアイレットやカードリングをあしらったドレスやスーツが登場。ビーズをグラデーションに刺繍したストライプのスカートスーツや、襟から肩にかけてスパンコールを刺繍したコートなど、クチュールライクな作品も健在。ワイヤーをハンドニットしたカーディガンや、ジッパーのスライダーを無数に縫い付けたコートなど、目新しいアイテムも。その合間に、シンプルなツイードのスーツが挟み込まれるが、今季は薄くて風通しの良い素材をあしらい、年々世界的に過酷になっている夏の高温に対応。
エイリアンの侵略になぞらえたコレクションであり、おどろおどろしい表現が散見されるものの、結局はアメリカ人らしいあっけらかんとしたオプティミズムを感じさせる内容となっていた。
ジャンポール・ゴルチエ(JEAN PAUL GAULTIER)


Courtesy of JEAN PAUL GAULTIER
2015春夏コレクションでプレタポルテコレクションを休止していた「ジャン・ポール・ゴルチエ」が、新たにデュラン・ランティンクをクリエイティブ・ディレクターに迎えてコレクションを発表。ケイ・ブランリー美術館を舞台にショーを開催した。
オランダのハーグ生まれのランティンクは、ヘリット・リートフェルト・アカデミーに通い、その後2017年にアムステルダムのサンドベルグ・インスティテュートを卒業。2024年にはLVMHプライズにて、カール・ラガーフェルド審査員特別賞を受賞し、今年はインターナショナル・ウールマーク賞を受賞。 そして4月に「ジャン・ポール・ゴルチエ」のアーティスティック・ディレクターに就任することが発表されていた。
これまでに見られたランティンクの強い表現は当コレクションでも十分に生かされ、肌の露出の多いセクシャルで挑発的なアイテムが多く見られた。綿入りの大きな胸のオールインワンでスタート。胸毛の生えた男性の裸のフォトプリントのオールインワンや、毛むくじゃらの裸をプリントしたブラとスカートのアンサンブルなど、目のやり場に困るアイテムが登場。サイドから見るとS字になっている、ギリギリ胸が隠れるドレスや、身体を挟むようにして固定するドレスなど、斬新なアイデアによるアイテムが随所に見られた。コーンブラやトレンチコートといった「ジャン・ポール・ゴルチエ」のアイコンから距離を置き、自らのクリエーションに徹する姿勢を見せていた。
ショー終了後には、ジャン・ポール・ゴルチエ本人がデュラン・ランティンクと抱き合って互いに落涙する姿が目撃されている。
キコ・コスタディノフ(KIKO KOSTADINOV)


自由で自分らしくいたいとする女性に向けて服作りをした「キコ・コスタディノフ」。ブランド創設時からの根本的な姿勢に立ち返り、素材・構造・バランス・プロポーションを探求する純粋な楽しさを追求したという。
フェティッシュな作風を持つアメリカ人アーティスト、クリスティーナ・ランバーグの作品からも影響を受け、彼女の描く構築的で彫刻的、そして官能的な表現を、円形のショルダーやペプラムなどに反映。本人からの協力で、二点の作品のフォルムをドレスにあしらっている。
また、リナ・ヴェルトミュラー監督の1972年の映画「ミミの誘惑(The Seduction of Mimi)」に流れる、 1970年代のイタリア映画の享楽的なムードや温かみのある色彩からもインスパイア。
異なるファブリックをパッチワークし、意外性ある色彩の組み合わせで独自の世界観を築いて来た「キコ・コスタディノフ」だが、今季はより一層アーティスティックな表現を推し進めていた。
アンリアレイジ(ANREALAGE)


Courtesy of ANREALAGE/Photo by Koji Hirano
美術教育を受けていない障害者による作品を様々な形で活用する、岩手県の企業、ヘラルボニーとコラボレーションをした森永邦彦による「アンリアレイジ」。今季は中川ももこや鳥山シュウといった18名の作家による作品を、京セラの技術で水を使わずにファブリックにプリント。装飾的なフリルを電動で動かす装置を内蔵したドレスに仕立てた。
ルックによっては、ネコのような尻尾が動くバックをコーディネート。これはユカイ工学とのコラボレーションで、尻尾の機械構造を応用したものが今季の動くドレスの制作に繋がったという。
後日、先述の作家によるライブペインティングのイベントが開催されたが、そこで森永は「ヘラルボニーに新しい美しさがあることを教えてもらい、異彩を放つ作家作品を見た時の感動を発信したいと思った」と語っていた。
ヘラルボニーの作家作品をまとった各アイテムは、色鮮やかで享楽的。そこにロボット工学による人工的な動きが加わるのだが、得も言われぬほど有機的に感じられ、表現に窮する程に感情が揺さぶられる。前シーズンとは明らかに異なる感動があったのだった。
アンダーカバー(UNDERCOVER)


パリ市内のショールームにて最新コレクションをプレゼンテーション形式で発表した、高橋盾による「アンダーカバー」。35周年を記念した“But beautiful”コレクションを継続させ、非現実的な歪みやひねりを加えて、これまで通りのシュールレアリスティックな表現を見せている。
コートの脇には裏地が飛び出したかのような別布の装飾が付き、湾曲した見頃にはバラバラの大きさのボタンが取り付けられる。
カーディガンとTシャツとスカートのセットアップかと思いきや、実は一体型ワンピースになっていたり、「シャネル(CHANEL)」風の襟無しジャケットを引き裂いたシフォンで表現したり。それらは、「不完全な美しさ」を具現化し、これまでに無い魅力を生み出している。
アーティストのアンヌ・ヴァレリー・デュポンとのコラボレーションも登場し、解剖図のような臓器と花を飾ったドレスを作成。毒気の中に愛らしさが潜む、引き込まれるような魔力を備えた作品となっていた。
トリシェジュ(TORISHÉJU)


ナイジェリアとブラジルの血を引くイギリス人、トリシェジュ・デュミによる「トリシェジュ」は、エスパス・カンボン・キャプシーヌにて公式カレンダー外でショーを開催。
トリシェジュは、ロンドン・カレッジ・オブ・ファッション出身で、セント・マーティンの修士号を終了。フィービー・ファイロ時代の「セリーヌ(CELINE)」に参加し、2023年に独立。今年のLVMHプライズではサヴォワールド・フェイール賞を受賞したことで脚光を浴び、ドーバー・ストリート・マーケットのバイヤーチームや英国のジャーナリストが大集合。注目度の高さを見せた。
年一回のコレクション発表をし、これまで通りファーストルックはナオミ・キャンベルが務めた。
今季は、画家アルブレヒト・デューラーの作品や本人のスタイルからインスパイア。袖を内側に入れ込んだようなディテールのワンピース。デューラー風のカスケットを重ね、中世風のケープコートを合わせるが、あくまでもエッセンスとして活用しているだけで、彼女ならではのスタイルとフォルムを貫いている。トレンドから距離を置き、自らの作風を崩さない、その独自性に驚かされる。期待値の高さに納得させられたのだった。
ジュリ ケーゲル(Julie Kegels)


パリ16区に位置する地下鉄6番線のパッシー駅の高架下を会場にショーを行った、アントワープを拠点とする「ジュリ ケーゲル」。オフィスから夜の社交場まで、常に動き続ける現代の女性をイメージし、演劇での早変わりからインスパイアされたという数秒でシルエットが変化するアイテムを考案。今季はコレクションタイトルを“Quick Change”とした。
32人の女性の声やエレクトリックピアノだけを伴奏にしたフリートウッド・マックの「Dreams」など、生活の中で感じられる不安や希望など揺れ動く感情を音でも表現。不完全な中の完全さを見せ、シワや汚れ、DIY風の歪みといったものも魅力の一つとなり、「時間」や「記憶」の痕跡として肯定的に捉える姿勢を見せた。
ブラやキャミソールなど、フェミニンなランジェリーの要素を散りばめ、スパンコールを閉じ込めたシースルーのスカートやバスルを思わせるパーツの付いたベルトなどが官能的な側面を加える。
フランドル風の静物画をそのままアップサイクルしたドレスも登場。フェミニンでアーティスティック。その独自の表現は中毒性を持ち、今後、様々な女性から共感を呼び、支持を集めそうに思わせた。
取材・文:清水友顕(Text by Tomoaki Shimizu)
画像:各ブランド提供