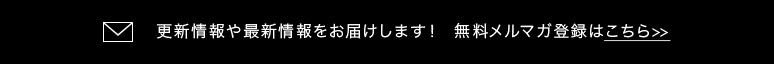PICK UP
2025.09.12
【2026春夏東京 ハイライト3】楽天ファッションウィーク東京2026春夏ウィメンズ ボディコンシャスを軸に新たな実験

写真左から「チカ キサダ」「フェティコ」「ムッシャン」「ナゴンスタンス」
楽天ファッションウィーク東京(Rakuten Fashion Week TOKYO)が閉幕した。今シーズンのウィメンズでは、女性の身体の美しさを強調するボディコンシャスを軸に、アートやオカルト、スポーツ、解剖学など多様な要素を取り込んだ実験的なコレクションが相次いだ。「チカ キサダ(Chika Kisada)」は“痕跡”をテーマに衣服の常識を解体し、「フェティコ(FETICO)」は設立5周年を機にコスメとの協業で新たな表現を探った。「ムッシャン(mukcyen)」や「ナゴンスタンス(någonstans)」、「セイヴソン(Seivson)」も独自の視点で未来や自然、女性の強さを描き出した。
チカ キサダ(Chika Kisada)


幾左田千佳がデザインする「チカ キサダ」のテーマは“Trace(痕跡・記憶・輪郭)”。東京・代官山のTHE FACE DAIKANYAMAで発表した今回。前回の大規模な会場から一転し、今回は親密な距離感を生かしたプレゼンテーション形式を採用し、ブランドが持つ実験性を凝縮して示した。
コレクションは、ヌードカラーのジャケットと透けるドットのトップスに、ボロボロに裂かれたようなタイツを合わせたルックから幕を開けた。冒頭から漂うのは過激なパンクのムード。裾が下着のように伸びたニットに、ソファーのように膨らんだストライプのスカートを組み合わせるなど、衣服の常識を解体し、異質な要素を接続する姿勢が際立った。フード付きジャケットやストライプのシャツも登場し、80年代の日本人デザイナーやアントワープ派を想起させるアバンギャルドな構成が続く。
胸元に「OPERA HOUSE」や「JUST BE QUIET?」と記されたTシャツは、下半分が糸のようにほどけ、透けるニットドレスへと変容する仕掛けが施されていた。そこに合わせられたのは穴の開いたダメージデニム。逆に、肩部分が糸のように解けた黒いドレスの上に、裂かれたタイツのようなシャツを重ねる造形も見せた。袖を外して肩パットを露出させたストライプジャケットの下にも、引き裂かれたインナーが合わせられている。布地の裂け目や糸のほつれを用いた表現が随所に散りばめられ、服そのものが痕跡を刻むように存在していた。
中盤では、ニットにカラフルな玉を付け、中央を透かせたバレリーナ風スカートが登場。バレエ的な繊細さと、グランジ的な粗野さが交錯する。さらに、トレンチコートにスパンコールのスカートを組み合わせるなど、対比的な要素を同居させるスタイルが目を引いた。ポロシャツの中にアウターをドッキングしたデザインや、一枚のブルーシャツの中に異なるストライプシャツを共存させる構造もあり、衣服の中に複数の衣服をコラージュするような実験が試みられた。
終盤にかけては、裾が溶けて流れていくように見えるトレーナーや、時間のずれを切り取ったようなニットワンピースなどが続いた。ダメージ加工を超え、「引き裂かれた痕跡」を強調することで、服に内在する動きや記憶を視覚化する試みといえる。全体を通じて、コラージュやダブルイメージ、超現実主義の発想を取り込みながら、身体と都市、時間と記憶を重ね合わせるような実験的なコレクション。
フェティコ(FETICO)


「フェティコ」は、楽天によるブランド支援プロジェクト「by R」枠で2026春夏コレクションを発表した。設立5周年を迎え、節目となる今シーズンはホリスティックビューティーブランド「スリー(THREE)」と協業。ファッションとコスメという異業種の掛け合わせによって新たな表現を探り、日本のファッションシーンをさらに活性化することを目指した。
会場は国立代々木競技場第二体育館の中に設けられた白いボックス型の特設空間。美術館のような静謐さの中で、コレクションはスタートした。そこに登場したのは、女性の身体美を強調する数々の造形。黒いベールで顔を覆い、下着を思わせるルックやボンテージを想起させるフェティッシュなスタイルは、単なる装飾を超えて身体と手仕事の共存を表現していた。
デザイナーの舟山瑛美が着想を得たのは、ドイツの芸術家レベッカ・ホルンと写真家イリナ・イオネスコという二人の女性アーティスト。ホルンは身体の拡張や制約の昇華を作品に込め、イオネスコは退廃的な美学の中で女性の神秘性を描き出した。その姿勢を取り込むことで、「フェティコ」は「女性はこうあるべき」という規範から解放された自由な自己表現を追求している。
コレクションは、朱赤のニットや赤いドレス、花柄スカートなどの鮮やかな色彩を交えつつ、黒・ベージュ・アイボリーを基調に展開。レースのトップスとミニスカート、透け感を生かしたドレス、ギリシャ彫刻を思わせるヌードドレープなどが続き、陰影の中に浮かび上がる身体のラインが際立った。「アライア(ALAÏA)」を彷彿させるシルエットの強さも見られ、日本の職人技を駆使したレースや、ラグジュアリーブランドからも注目されるデニムを取り入れたドレスが存在感を放った。
さらにラウンジウエア的なリラックス感をもたらすアイテムも並び、空港でも着られるような実用性を備えた白いジャケットやデニムシリーズがコレクションの幅を広げた。白いレースに身を包んだ花嫁を思わせる一群のルックは、5周年を象徴するような完成度の高さで観客を魅了した。
会場には「スリー」との協業による香りが漂い、モデルのメイクにも同ブランドの製品が用いられた。衣服と化粧品が融合する演出は、「フェティコ」が目指す“女性の身体と自己表現の再考”というテーマを一層鮮明に伝えていた。
舟山は楽天によるブランド支援プロジェクト「by R」で発表した理由について「小さな個人ブランドにとってショーを行うこと自体が大きな賭けで、コスト面での不安が常にあります。今回はその部分をしっかりサポートしていただけたことで、制作に集中できました。資金の問題で諦めざるを得なかったことも諦めずに取り組めたのは大きな助けになりました。さらに、多くの人に見てもらえる機会をいただけたことも、ブランドとして大きなチャンスだと感じ、強い気持ちで臨むことができました」と話した。
ムッシャン(mukcyen)


楽天ファッションウィーク東京2026春夏の開幕を飾ったのは、「JFW NEXT BRAND AWARD 2026」でグランプリを受賞した「ムッシャン」。デザイナー木村由佳が選んだテーマは“況; bracing”。日本でも話題となった「7月5日の予言」を背景に、未来への恐怖や不確実性を服に置き換え、身体と衣服の関係を鮮烈に描き出した。
会場は赤いライトで染められ、緊張感の漂う空気の中でショーはスタート。ファーストルックに登場したのは、穴の開いた透けるニットや白いトップスに下着風のボトムを合わせたルック。ボディウエアを想起させる挑発的な造形は、「ムッシャン」らしい身体美へのアプローチを象徴していた。続いて現れたのは、いくつもの穴を施したTシャツ型のドレス。首や腕を通す位置を自由に選び、何通りもの着方ができる構造で、ドレープが偶発的な美を生む仕掛けとなっている。
ショー全体に通底するのは、ボディコンシャスとドレーピング、レイヤリングの共存だ。スキンドレスや黒のカットソー、スカートには美しいドレープが重なり、身体を覆いながらも陰影を際立たせる。スキンカラーのブルゾンやスカートには下着風のアイテムを合わせ、マニッシュとフェミニン、アウターとインナーを交錯させた。複数の要素を一つのアイテムに組み込み、装飾とリアリティを融合させる試みが随所に見られた。
アイテムの幅も広い。ミリタリー要素を取り込んだボディコンシャスドレスや、ギリシャ彫刻を思わせるドレープを加えたTシャツ、イスラムの女性服を思わせるデザインも登場。ジャケットはボタンで袖や腰部分を取り外せ、スポーツウエアのような機能性を備える。パンツには膝に切れ込みを入れ、ストリート風の要素を加えた。着物にもコートにも見えるデザインは、帯のようなベルトで締めることでドレスへと変化する。文化的な要素と現代的な構築が交差する造形は、ブランドのアイデンティティーを更新する試みでもあった。
後半には、フリンジで体を覆ったドレスが登場。歩みとともに揺れるフリンジは軽やかさを際立たせ、銀色のウイッグを着けているかのような幻想的な印象を与えた。ラウンジウエアに見えるアウターや、パジャマ感覚で着られるリラックスしたアイテムも加わり、室内から外出までシームレスに対応する服の提案が打ち出された。木村が語る「日常と非日常をつなぐリアリティ」が目に見える形で表現されている。
ブランドの象徴である「セカンドスキン」シリーズには、今季新たに機能性を付加。肌に近い色合いや素材感を生かしつつ、着心地と即応性を兼ね備えたデザインが加わった。身体を包み込み、同時に社会の中へ踏み出すことを促す「構え」としての衣服を提示している。
木村は「日本だけでなく海外の人にも見てもらいたい。ブランドを象徴する素材に、より機能性を持たせる実験を始め、女性にとって良いものを提供することが最大の目標」と語り、ブランドの次なるステージを見据えた。ムッシャンが描くのは、予測不可能な未来を恐れず、自らの身体と向き合いながら日常を生きるための服。その挑戦的なメッセージと構築的なデザインは、開幕にふさわしい強い印象を残した。
ナゴンスタンス(någonstans)


Courtesy of Japan Fashion Week Organization
東京・江東区有明のBrillia RUNNING STADIUMで発表した「ナゴンスタンス」。テーマは“Mountain Trail”。夏山を歩くときに感じる静けさや景色の移ろいを軸に、自然とスポーツ、そして未来性を調和させたスタイルを提示した。
会場はブルーのトラックに白線が引かれたランニングスタジアム。うだるような暑さの中、モデルたちは白線上を進んだ。膨らむオーバーサイズのコートに水着風インナーを合わせたルックや、自然光を思わせるマルチストライプのコート、イエローのアウターが続く。いずれも風をはらみ軽快に揺れ、自然との親和性を示す色使いが印象的だった。
デザインの軸には、サイクリングやエアロビクス、トレイルランニングといった身体の自由な動きがある。スポーツ由来のボディコンシャスなシルエットやサイクリスト風のスタイルを、花や草のような淡く美しい色合いで表現。未来的なハイテク素材を思わせる半透明のコートも登場し、機能性をミニマルに昇華させた。
岩肌や断崖の「鋭さ」と稜線の「滑らかさ」という相反するフォルムは、立体的なパターンで服に落とし込まれた。山脈を思わせる膨らみを持ちながら軽さや透明感を備えたコートやドレス、スカートは、デザイナー自身の登山体験を反映しているようだ。山やキャンプなどアウトドアの場面でも楽しめる実用性を備えつつ、都市空間にもなじむウエアへと仕上げられている。
後半には山の風景をストレートにプリントしたドレスやスポーツウエアが登場。山のうねりや凹凸を思わせるパターンや立体感を強調し、ブルー、イエロー、ピンクなど鮮やかな色彩を展開した。60年代の未来派を彷彿させるミニドレスやネオンカラーと自然色の組み合わせは、未来と自然の共存を象徴する。時折差し込まれるスキンカラーのルックは、身体の美しさを際立たせる効果を担っていた。
色は初夏の山々に息づく重層的な緑、山小屋の温もり、高山植物の可憐さ、岩のグレイッシュな力強さ、そして空と雲のコントラストまでを抽出。帽子など実用的なアイテムも加わり、爽やかなグリーンと未来的ムードを調和させたコレクション。デザイナーの植田みずきは「ずっとやりたかったショーなので、今は少し興奮しています。会場の中からは外の様子が全く見えなかったので、どう映っていたのかドキドキしましたが、やり遂げた達成感があります」と笑顔。
自然のフォルムを服に写し取りながら、スポーツの動きや都市生活にも応える機能性を融合させたナゴンスタンス。自然と未来、日常とアウトドアを軽やかにつなぐ姿勢が、ブランドの方向性を明確に示していた。
セイヴソン(Seivson)


台湾出身デザイナーのヅゥチン・シンが手掛ける「セイヴソン」は、渋谷ヒカリエ・ホールBで2026春夏コレクションを発表した。テーマは“AFTERLIGHT”=“衣を骨とし、女性を縫い上げる”。女性の体を構成する骨格や血管、成長の過程で刻まれる痕跡を赤い糸で可視化し、存在の強さと脆さを同時に描き出した。
ショーは台湾製ポリエステルにランダムなワッシャー加工を施したジャケットと、骨や血管をイメージしたニットドレスからスタート。ウエストを絞り女性の体を際立たせたジャケットやスカート、凹凸を加えたブルゾンやコートが続き、糸のほつれから脚を露出させるニットスカートは80年代のアバンギャルドやダメージデニムを想起させた。ボディコンシャスなドレスや透ける素材を用いたシャツ、パンツも登場し、女性の身体線を強調する構成が際立った。
象徴的ルックに挙げられたのは赤いニットのコーディネートだ。繰り返し登場するほつれや透け感のあるニットは、傷やしわといった経験の痕跡を体現。肌を見せるデザインは「台湾人としての本質を示すもの」として位置づけられ、デザイナー自身も「女性が成長する中で変化する部分と、変わらない骨格を対比させた」と語った。赤と黒を基調に構築された衣服は、女性の存在の重さを象徴する装置となった。
リリースでは「Fiber(繊維)」「Bone(骨格)」「Trace(痕跡)」の3シリーズが示され、さらにサステナブル素材を扱うバイオワークス(BIOWORKS)との協業も発表された。糸を解体し再構築するプロセスを通じて、女性の身体と歴史に潜む強靱さと脆さを同時に表すことを狙った。プリーツ加工を施したクロップドジャケットや甲冑を思わせる赤のミニスカートも登場し、フェミニンとマニッシュを往来しながら体の美しさを際立たせた。
台湾の気候や歴史を背景に素材を選んだ点も特徴だ。シンは「台湾は断裂と再生を繰り返してきた土地。女性の体と同じように歴史の痕跡を刻んでいる」と語り、島国特有の文脈を服に織り込んだ。ポリエステルのワッシャー加工は、成長と経験の積み重ねを表現する技術として今季も用いられている。
また、帽子ブランド「カシラ(CA4LA)」とシューズブランド「スブ(SUBU)」とのコラボレーション商品も披露された。台湾と日本を拠点とする両ブランドと「国境を越えて意気投合した」といい、今後の展開を示唆する取り組みとなった。
オートモードヒラタ(Haute Mode Hirata)


「オートモードヒラタ」は、渋谷ヒカリエ・ホールAでランウェイショーを開催し、故・平田暁夫の生誕100周年を記念する特別コレクションを発表した。娘の平田欧子、孫の平田早姫と平田翔による家族3人のモディストが制作した31点の帽子を中心に据え、衣装は〈TOKYO FASHION AWARD〉受賞者の砂川卓也(「ミスターイット(mister it.)」)、玉田達也(「タム(Tamme)」)、彫刻的な服づくりで知られる岡﨑龍之祐(「リュウノスケオカザキ(RYUNOSUKEOKAZAKI)」)が手掛けた。帽子を主役に据えた舞台は、伝統と革新を往還する姿を鮮やかに示した。
ショーは、一目で平田暁夫を想起させるクラシックな帽子のフォルムを黒く染めた作品から幕を開けた。透ける素材と黒い衣服を組み合わせた造形や、花を飾ったり帽子そのものが花となったようなデザインが続く。さらに、帽子とキャップをドッキングさせたスタイルや、糸を残したままの仕立てで制作のプロセスを想起させる作品、色の変化を強調した実験的な造形も登場。前衛舞踏を思わせる衣装やアート作品のようなシルエットとともに、クラシックを現代的に再構築する姿勢が随所に表れた。
同ブランドは1955年に創業。創設者の平田暁夫は1962〜65年にかけてパリの巨匠ジャン・バルテに師事し、日本人として初めてフランスのオートクチュール技法「オートモード」を体得した。帰国後は皇室の帽子制作を担い、「コム デ ギャルソン(COMME des GARCONS)」や「ヨウジヤマモト(Yohji Yamamoto)」、「イッセイ ミヤケ(ISSEY MIYAKE)」、「ハナエモリ(Hanae Mori)」、「ジュン アシダ(jun ashida)」など国内外のブランドとも協業。さらに、帽子学校で3000人以上を育成し、日本の帽子文化を牽引した。2011年にはスパイラルガーデンで展覧会「ヒラタノボウシ」を開催し、約4000点の白い帽子を天井から雲のように吊るしたインスタレーションで観客を圧倒した。
今回のショーはその延長線上にありながらも、帽子を「人がかぶり歩く」ことで魅力を引き出す構成に転換。クラシックなフォルムの再解釈に加え、ねぶた祭の和紙をチュールと組み合わせた素材、西陣織職人によるマーブル加工、京友禅技法を応用した和紙ボンディングレザー(京都レザー(KYOTO Leather)協力)など、新たな試みも随所に盛り込んだ。
舞台に登場した31点は、先代が残したチップを用いた作品から新たに生み出されたものまで幅広い。伝統的な手技と現代的な解釈、希少な素材と最新の技法を交差させた造形は、帽子が服の印象を大きく変える存在であることを改めて示した。
創業70周年、生誕100年という節目を迎えた今回のコレクション。平田暁夫が切り拓いた「帽子の過去・現在・未来」を体現。人と帽子の関係を問い直しながら、次世代へ受け継がれる伝統と革新の姿を浮かび上がらせた。
平田早姫は「展示ではなく、人がかぶることで帽子に命が宿り、輝きが増す姿を見せたかった。祖父・暁夫も常に『人を輝かせる帽子』を作り続けてきました。その思いを受け継ぎたい」とした上で、衣装との関係については「帽子を引き立てつつファッションとして完成させるため、ボディラインを活かしたシルエットやニュートラルな色合いを選びました。砂川卓也さん、玉田達也さん、岡﨑龍之祐さんの協力で帽子が際立つスタイリングができました」と説明。
また、「帽子は自分に合うものを見つけにくいと思われがちですが、洋服と同じように『お気に入りの一つ』を持ってほしい。新しい自分を発見できるような帽子を、これからも提案していきたい」と話した。
2005年に日本ファッションウィークが始まってから20年。参加ブランドは第1回の51から半減し、パリ、ミラノ、ニューヨーク、ロンドンに肩を並べるにはまだ道半ばだが、次に向けた育成や新たな取り組みは進んでいる。