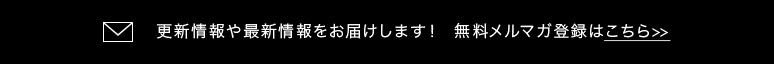PICK UP
2018.03.07
【宮田理江のランウェイ解読 Vol.47】2018-19年秋冬ロンドンコレクション
宮田理江のランウェイ解読 Vol.47
モード発信力がシーズンを重ねるごとに高まるロンドン・ファッションウイークは2018-19年秋冬シーズンに「ストリートラグジュアリー」のムードを強めた。ジェンダーフリー、シーズンレス、カルチャーミックスの勢いが加速。テイストの若返りが進んだ。


BURBERRY
(c) Courtesy of Burberry
17年にわたって、「バーバリー(BURBERRY)」を支えたクリストファー・ベイリー(Christopher Bailey)氏はカラフルでハッピーなランウェイでラストショーを締めくくった。レンガ造りの廃墟めいた建物を舞台に、ポジティブで楽観的なコレクションを披露した。
「Time」をテーマに、時を超えたタイムレスな作品を披露。1980年代から現代に至る「バーバリー」のアーカイブを、ロンドンらしいストリートカルチャーと交わらせた。レインボーカラーがランウェイを染め上げた。「LGBTQ+」コミュニティーへの連帯感を、シンボルカラーの虹色に込めた。虹色はキルティングジャケットやセーターなど様々なウエアに写し込まれて、何度も登場した。
ブランドアイコンと言えるトレンチコートはピンクの分厚い生地で仕立て、グラフィティ(落書き)風のモチーフを全体に施した。同じく、「バーバリー」の代名詞的なチェック柄もマルチカラーや特大化などのアレンジを加えて繰り返し用いられていた。ブランケット風のポンチョ、オーバーサイズのパーカ(フーディー)などで、ロンドンのユースカルチャーへの共感を示した。キャップやニット帽にもストリートシーンへのリスペクトが滲んだ。
柄をプレイフルに操った。異なるチェック柄を組み合わせたレイヤードはブランドの伝統をウィットたっぷりにモダナイズ。カムフラージュ柄やパッチワーク模様も投入。ブランドロゴまでカラーミックスで書き換えて見せた。ショーの直後から売り出す「See Now, Buy Now」式の先駆けとなったのもベイリー氏の功績だ。今回も一部を「February カプセルコレクション」としてすぐに発売した。
メンズとウィメンズ、春夏物と秋冬物が自然に混ざり合い、ジェンダーレスやシーズンフリーの景色を描き出していたのもベイリー氏の立ち位置を映す。テーマに「時」を選んで、自らの軌跡と「バーバリー」の歴史を交差させ、永遠に語り継がれるであろうタイムレスなラストコレクションにまとめ上げていた。


JW ANDERSON
(c) InDigital
「ジェイ ダブリュー アンダーソン(JW ANDERSON)」は初めてウィメンズとメンズのショーを統合して開いた。ジェンダーレスの流れが背景にあるのは当然だが、今回のコレクションでは、メンズ物を好んで買い求める女性が喜びそうなメンズアイテムがいくつも用意されていて、現代女性の自由なショッピングマインドまで織り込んだクリエーションと見えた。
ランウェイの真ん中に現代アートのキノコ状インスタレーションを置いた状態でショーがスタート。アイテム面で柱になったのはミモレ丈やロング丈のスカート。裾先が鋭角のハンカチーフヘムを多用して、着姿を弾ませた。カーキやベージュといった渋めのナチュラルカラーを軸に、アウトドアやユーティリティーの気分を乗せている。自然なドレープやしわがリラクシングな風情を漂わせる。マルチカラーのペイズリー模様、イエローからオレンジへのグラデーションは装いに彩りを添えていた。
全体に通じているのはストリートの気分だ。漫画風のイラストを配したニットセーターをはじめ、パーカ(フーディー)、ノースリーブ・トップスなどはロンドンのユースカルチャーを写し込んでいた。
カラフルなスニーカーにも街の空気とウィットフルな着想が感じ取れる。オレンジのアッパーにブルーのソールという強烈なカラーリングに加え、左右の色が違うシューレースが着こなしにインパクトを与えた。バッグ脇にまでスニーカー風のレースアップを施していた。
シーズンやトレンドをやたらと意識しすぎない、今回のコレクションは、慌ただしいモード界にスローダウンを促すかのよう。どこか懐かしげなムードにも、「ファッション時計」が今ほど駆け足ではなかった時代へと、針を巻き戻すような意識がうかがえた。


古田泰子デザイナーの「トーガ(TOGA)」は、英国と大陸を結ぶ列車「ユーロスター」の発着駅として知られるセント・パンクラス駅のビル構内にある未使用スペースをショー会場に選んだ。仕上げがフィニッシュしていない、粗削りな空間のムードは「UNRAP, TYPICAL, RELEASE」と名付けられた、従来のルールに縛られないコレクション内容にふさわしく見えた。
古典的なスカーフプリントを用いて、装いにエレガンスを注ぎ込んだ。単にスカーフを巻くのではなく、セットアップの脇や腰を丸くくり抜いて、内側からスカーフ柄をのぞかせるような、前シーズンから続く「服の解体」と組み合わせた演出が立体感を生んでいる。髪を包み込むスカーフ使いもクラシック感を帯びた。ベルトにもスカーフを配して、スカーフ使いの表現を広げてみせた。
マニッシュなジャケットとフェミニンなスカートといった、性差をねじり返すようなスタイリングが冴えた。ボクシーなテーラードジャケットも着丈を長めにしたり、ワイドパンツを組み合わせたりして、ずらしを仕掛けている。エメラルドグリーンのコートやワンピースはリュクスなたたずまい。ケミカルな光沢を宿したプリーツスカートはミステリアスにつやめいた。シルキーな質感がコレクション全体に上質感をまとわせていた。
深いスリットからのぞくインナー、ひるがえって顔を出す裏地などにビビッドカラーを用いて、重層的な着映えに仕上げている。裾を不規則に垂らし遊ばせるディテールも「不ぞろいの美」を生んだ。大ぶりのプレートを吊り下げた、太いゴールドチェーンのネックレスが視線を引き込む。バロック風のスカーフ柄、英国調テーラードの技法などを複雑にカルチャーミックスしてコスモポリタンなムードを醸し出していた。


ロンドン市内のパブをプレゼンテーション(展示会)会場に選んだのは「エムエム6 メゾン マルジェラ(MM6 Maison Margiela)」。壁や床、ソファなどをすべてシルバーホイルで覆って、一面の「銀世界」を作り出した。パブカウンター内のビールサーバーまでホイルでくるむほどの徹底ぶりだ。
メタリックシルバーで統一したのは、会場の景色だけではない。25ルックの全てでシルバーをキーカラーに据え、ほとんどのルックではシルバーオンリーのまばゆい着姿に整えた。全身を銀色で染め上げたルックはフューチャリスティック(未来的)なムードが濃厚。服とバッグ、ブーツに銀メッキを施したかのような徹底したシルバールックには、SF気分やウィットが感じられる。アルミホイルのような軽い質感ではなく、クロムを混ぜ込んだ重金属系の渋いシルバーを多用。鈍い銀色がダークな気分をまとわせている。
大襟のダブルブレスト・コートやレザーベスト、キルティングアウターなどと組み合わせたパンツルックが披露された。デニムジャケットもシルバーでコーティング。本来のアイテムとは別の表情を引き出している。口まで隠すフード付きのアウターは宇宙服のよう。パフィなジャケットは遊園地のバルーンを思わせる。オートバイ乗りがかぶるヘルメットはバッグに置き換えた。ミラーボールのタイルで仕立てたようなウエアはブランドのアーカイブに由来。ディスコ時代の郷愁を誘う。
アンディ・ウォーホルのアトリエだった「ファクトリー」を模倣したような舞台づくりが示す通り、コンセプチュアルな趣が深い。未来感覚を押し出しながらも、どこかレトロな風情があり、科学やテクノロジーがいっそう身近になった時代への皮肉っぽいまなざしを感じさせた。


(c) Courtesy of Richard Quinn
今回のロンドンで最大の話題を集めたのは、まだデビューから2度目のコレクション発表という若きデザイナー、リチャード・クイン(RICHARD QUINN)氏だった。その理由は英国のエリザベス2世女王がフロントロウに座ったから。女王がロンドン・ファッションウイークでランウェイショーを見るのは史上初の出来事だ。
女王が来場した目的は、陛下の名前を冠したファッション賞「クイーン・エリザベス2世・ブリティッシュ・デザイン・アワード(Queen Elizabeth II Award)」のトロフィーを手渡すためだ。初の受賞者に選ばれたのがリチャードだったことから、今回の来場が実現した。このような賞の創設や女王の来臨にも英国が次世代のクリエイターを育てる意欲が認められる。
まだ2016年にセントラル・セント・マーティンズを卒業したばかりの新星だが、実力は折り紙付き。花柄プリントで名高い百貨店「リバティ」でデビューコレクションを発表していることでも分かる通り、フラワーモチーフの操り方に長けている。今回も花柄をふんだんにあしらって、装いに華やぎと生命感を注ぎ込んでいた。
新鋭ならではの大胆な発想でアレンジしたのは、花柄や水玉模様のスカーフ。色やモチーフが異なるたくさんのスカーフをつなげてドレスのように仕立てたり、顔を覆面のように覆ったり。スカーフをパッチワーク風に何枚も組み合わせて、カラフルな着映えに導いている。ゴージャスに布をたなびかせるワンピースも打ち出した。キャンディーの包み紙を思わせるきらびやかな生地のマント風パーツをひるがえす、ダイナミックな末広がりシルエットのドレスがランウェイをグラマラスに彩った。
パッドで膨らませたパフィなジャケットでボリュームを弾ませた。花柄で飾ったフルフェイス式ヘルメットはサプライズな印象。髪もヘッドアクセサリー風にスカーフで包んだ。ドラマティックに裾を躍らせたドレスに象徴される、シルエットの構想力は、新鋭を送り出し続けるロンドンならではの懐の深さを証明していた。


PORTS 1961
「ポーツ 1961(PORTS 1961)」はファブリックへの敬意をコレクションに込めた。本来は服の内側にひっそりと記されるはずの「MADE IN ITALY」「MADE IN ENGLAND」の産地表示を特大サイズの文字でロゴのようにまとった。日本製のウールも使われていて、ケープには「ウール」「羊毛」という日本語が大きく写し込まれていた。
現代アートの殿堂「テート・モダン」を会場に、ファブリックの美をうたい上げた。表と裏でアニマル柄の模様が異なるダブルフェイスのロングアウター、グロッシーにコーティングされたコットンコートなど、素材感にひねりを加えたこしらえにクラフトマンシップがうかがえた。ポンチョ風のロング丈アウターのようなオーバーサイズのフォルムが多用され、のどかな景色がランウェイに広がった。全身をくるむ感じのシルエットは、着る人を守るかのような見え具合。オーバーサイズの仕立てでも、マスキュリンなテーラーリングがだらしなく見せず、むしろ大人のゆとりを感じさせた。
指先まで隠すほどのスーパーロング袖も繰り返し登場。気負いを遠ざける、程よいルーズ感を示した。ニットセーターはひじから先のリブ編み部分が異常に長い。無地のワンピースは1枚布の穏やかな表情がのどかなムードを漂わせている。フラットソールの靴もリラクシングな足元に見せていた。ボリューミーな量感がかえってスレンダー感を引き出している。切り替えやレイヤードで重層的なイメージを印象づけた。スリーブレス・ワンピースは深いVネックがシャープな表情。左右で袖丈が極端に異なるドレスはアシンメトリー(不ぞろい)がエレガンスを薫らせる。
天の河のようにきらめくホログラフィー加工を施したロングフリンジは首元から膝下まで長く続いて、落ち感を際立たせていた。カシュクールやアシンメトリーもありきたりのバランスを崩し、優美な縦長イメージを際立たせている。全体にファブリックへの自信がクリエーションを支えている。あえて裏地を見せるような演出にも、素材と職人技への自負が感じ取れた。


MARGARET HOWELL
「マーガレット・ハウエル(MARGARET HOWELL)」はメンズとウィメンズを統合したランウェイショーを開き、トラッドとワークウエアを響き合わせた。性別をまたぐ「ジェンダーレス」のテイストも濃くした。
グレーのニットトップスと白っぽいトラウザーズパンツで幕開け。黒系ベレー帽がアンドロジナス(中性)感とミリタリー風味を添える。ニットカーディガンをマフラー風に首に巻き付ける、アイキャッチーなアレンジは意外感が高い。プリーツスカートと白アンクルソックスでスクールガール風に整えている。白ハイネックの上からチェック柄シャツを着て、ボタンをきっちり留める重ね着は懐かしげな風情。シャツの袖先ボタンを外し、カフスを遊ばせる小技を繰り返し披露した。
ノスタルジックな雰囲気とナチュラルな気分が入り交じる。ピーターパンライクな飾り襟や、マルチカラーのペイズリー柄ワンピースにもレトロが薫る。ワックスを利かせたレザージャケットは窮屈めの仕立てが生きて、しわの表情が深い。ツイード生地のジャケットに、綿のワークパンツという異素材ミックスがユーティリティーコーディネートの公式を書き換える。実用テイストとクラフト感が穏やかなムードを寄り添わせていた。


Photo Credit: Mitchell Sams
「ハウス オブ ホランド(HOUSE OF HOLLAND)」は持ち味のユーモアに磨きを掛けた。ヒップホップが勢いづいた1990年代頃のストリートテイストを乗せて、若々しい装いに仕上げている。ファーストルックのデニムジャケットは斜めに切り替えを施し、赤とインディゴの大胆なツートーンを試みた。ワークブーツは足の甲に飾りベルトを巻いて表情を変えた。ボールを輪っか状に連ねたビッグイヤリングは全ルックに添えている。
ディテールにウィットをちりばめた。ピンストライプの端正なスーツには登山ザイル風のロープベルトを巻き、端にはカラビナをぶら下げた。デニムの長袖ジャケットは肩口にファスナーで裂け目をこしらえた。あえてちぐはぐなマッチングを試み、ずれ感を醸し出している。トレーニングウエア風セットアップにはクラッチバッグとドレスシューズを引き合わせた。テーラードジャケットはカムフラージュ(迷彩)柄で染め上げている。
耳まで覆うほどたっぷりしたボリュームのキルティングジャケットはラッパーやスケーターへの気分を帯びる。ロゴ入りのレザーキャップ、レタード・パーカ、大襟のスタジアムジャケットなどはユースカルチャーの空気を呼び込んだ。ビッグロゴのマフラーは長く垂らし、着姿を弾ませていた。タータンチェック柄のスーツをはじめ、迷彩模様、ストライプ、ドット柄、フローラルなど、ブランドのDNAとも呼べそうなモチーフを詰め込んだ。複数のモチーフを響き合わせる「柄on柄」も装いにファニーなざわめきをもたらしている。
フォーマルとストリートのいたずらっぽいマリアージュで、新たなリアルスタイリングを提案している。着飾らないミレニアル世代を意識した「everyday wardrobe(日常の着こなし)」を打ち出し、コレクション全体を若返らせていた。

リチャード・クイン氏とエリザベス女王
(c) Courtesy of Richard Quinn
今回のロンドンではポジティブさや楽観、ウィットを写し込んだクリエーションが相次いだ。ダイバーシティー(多様性)への目配りが強まり、性別や民族、年齢にとらわれないミックステイストが一段と浸透した。複数のモチーフを重ね合わせる「柄on柄」、ボディーラインを拾わず性別をぼかすオーバーサイズ、「LGBTQ+」への連帯を示すレインボーカラーなども、多様な住民と文化を受け入れ続けるロンドンらしい懐の深さを物語る。時代に爪を立てる挑戦的な試みも目立ち、モードの発火点、ロンドンの健在ぶりを示していた。
 |
宮田 理江(みやた・りえ)
複数のファッションブランドの販売員としてキャリアを積み、バイヤー、プレスを経験後、ファッションジャーナリストへ。新聞や雑誌、テレビ、ウェブなど、数々のメディアでコメント提供や記事執筆を手がける。 コレクションのリポート、トレンドの解説、スタイリングの提案、セレブリティ・有名人・ストリートの着こなし分析のほか、企業・商品ブランディング、広告、イベント出演、セミナーなどを幅広くこなす。著書にファッション指南本『おしゃれの近道』『もっとおしゃれの近道』(共に学研)がある。
|